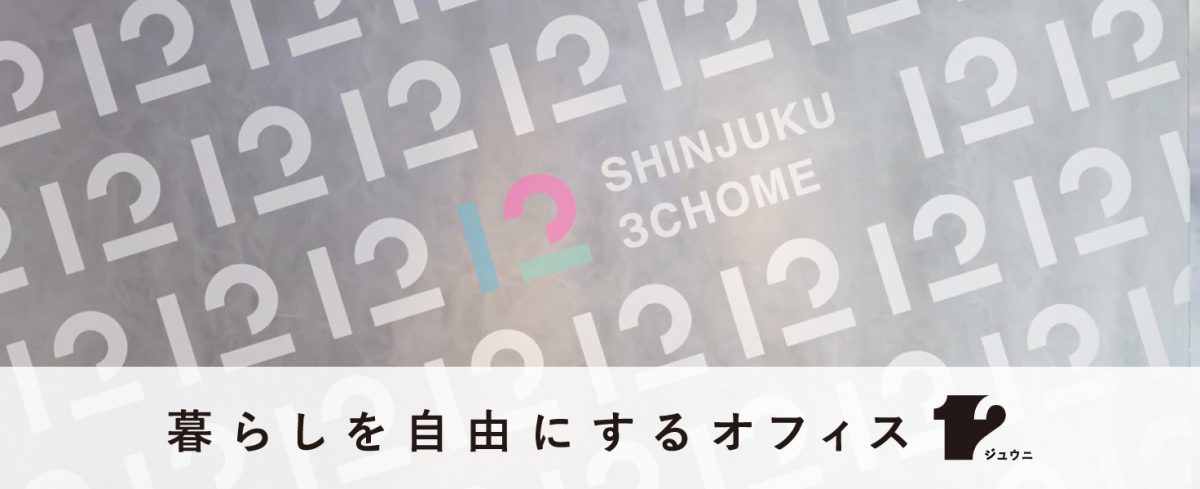まちとくらしの再構築
〈BUKATSUDO〉
本記事は、様々な土地を旅して回るフォトジャーナリストが、「リノベーションによる再生」に注目し、そうした土地を訪問し、滞在して綴るフォトエッセイです。
地元市民の発意によって誕生したマリンタワーが、長期の改修工事に入る(2019年4月〜2022年3月予定)と知った。横浜を代表する観光名所として君臨しながらも一時期経営難により閉鎖されるなど、紆余曲折とともに市民に愛された横浜港のシンボルだ。94mという程よい高さから、横浜の今を俯瞰できるかもしれないと思い立ち、展望台に登ることにした。

眼の前に横浜港が開け、山下公園が眼下に見え、みなとみらいも外国人墓地も視界に収まる展望台からの眺めは、なかなか素晴らしい。高層ビルが林立しているわけではないので、30階という高度は、街の成り立ちを知るのにちょうどよい。海を背にして街が広がっているような印象を受ける東京に対して、横浜は海に向かって街が展開していると感じる。だからこそ港町なわけで、当然といえば当然なのだが、海を感じることのできるレイアウトは心を浄化し、開放感をもたらしてくれる。
私は3年前まで、アルゼンチンの首都ブエノスアイレスで生活していた。その頃、ラプラタ川の対岸にあるウルグアイの首都、モンテビデオをいつも羨ましく思っていた。ラプラタ川と大西洋が交わる河口に背を向けて広がるブエノスアイレスはどこか息苦しく、対してモンテビデオは、大西洋に向かって街が形成されていて、どこを歩いていても海を感じることのできる心地よさが備わっていたからだ。横浜はそんな感情を思い出す街だ。


1930年代に流行したという和洋折衷のファサードが目を引く神奈川県庁・本庁舎、アラビア半島のどこかにいるような錯覚をもたらしてくれる横浜税関・本関庁舎を通り過ぎながら、みなとみらい地区へ歩いた。
みなとみらいはその昔、造船所だった。帆船日本丸を係留する「日本丸メモリアルパーク」と、横浜ランドマークタワーの隣にある「ドックヤードガーデン」。この2つが三菱重工業株式会社横浜造船所の名残で、いずれも国の重要文化財に指定されている。日本に現存する商船用石造りドックとしては最も古い「旧横浜船渠第2号ドック」を復元したドッグヤードガーデンはイベントなどでも利用され、「みらい横丁」という飲食店が、建物を取り囲むように軒を連ねている。



ところで、どうして私が横浜を徘徊してドッグヤードガーデンへやってきたかというと、港町で感傷的な気分に浸りたかったわけではなく、ワイワイと鍋を囲むためだった。ただし、向かった先はそうした居酒屋の類ではなく、とあるシェアスペース。ある時、桜木町で急な仕事を片付ける必要が生じ、ドロップイン可能なコワーキングスペースを探したときに利用した‘BUKATSUDO’という場所だ。
ラップトップと睨めっこをしたコワーカーたちが仕事に打ち込む横に広々としたキッチンがあって、そこで料理教室のようなものが行われていた。不思議に思い話しかけたところ、「鍋部です」という答えが返ってきた。そして誘われるがまま、再び‘BUKATSUDO’を訪れたというわけだ。


水曜日の夜、19時を回ることになるとキッチンに15名ほどが集まっていた。エプロンの下に見える衣服から察するに、参加者の大半は仕事帰りと思われる。中には私と同じく初めて参加する人もいるようだ。一同は作業を分担しあい、手際よく鍋の仕込みをはじめた。

47都道府県の鍋物を作るという鍋部のこの日のテーマは「のっぺい汁」。越後湯沢のスキー場へ通う部員が見つけてきたレシピだ。皆がワイワイと談笑しながらひとつの目的に取り組む様子は、まさに放課後の部活動のような雰囲気を思い起こさせてくれる。参加者のひとりが「年齢・性別・職業関係なく『初めまして』の人たちともすぐに仲良くなれる」と言うように、緊張感のある都会での生活とは対極の、自由で温かみのある雰囲気が何だか心地よい。


「ウマッ!」
干ししいたけの戻し汁とごぼうの匂いがふんわりと香り、海の幸が里芋のとろみと溶け合う。新潟の地酒が振る舞われると会話は更に弾む。* 野毛ツアーをやろうとか、女子会をセッティングしようとか、または大型連休が話題にあがると「リトウ部」の女性がマニアックな島旅の情報を教えてくれる。こういうやり取りの中から新たな部活が生まれることもあるといい、「レコード部」「哲学部」「昭和文化研究会」「ヨガ部」「餃子部」「くだもの部」などが活動していると知った。
* 野毛とは横浜随一の飲み屋街とも言われるエリアのこと
ちなみにこうした部活動は年に一度の「BUKATSUDO文化祭」で体験入部ができるらしい。さらに俳人・堀本裕樹さんと俳句を学ぶ句会、作家本人が登場する「贅沢な読書会」、コピーライターの阿部広太郎さんが主宰する「企画でメシを食っていく」など、ユニークかつ豪華なラインナップによる講座やトークショーも随時行われている。

BUKATSUDOには様々なスペースが有った。演劇やセミナー、結婚式の2次会など多目的に利用される‘HALL’やヨガ、フラ、キッズバレエなどで使用される‘STUDIO’があり、在住者や在勤者からも評判の良いコーヒースタンドが併設されている。そして‘BUKATSUDO’いう風変わりな名を持つ場所だけに‘BUSHITSU’と名づけられた一角が存在する。
そこはまさに「行けば必ず誰かがいる」、放課後の拠点だった部室のような佇まいを見せる月極のレンタルルームなのだが、シナリオ作家、クリエイティブ・ディレクター、手芸家、税理士など様々なバックグラウンドを持つ人々の活動の拠点となっている。



窓に「レコード部」と書かれた‘BUSHITSU’で作業に没頭する人がいた。株式会社セオ商事/GUILDのクリエイティブ・ディレクターである瀬尾さんだ。独立して仕事場を探していた時に‘BUKATSUDO’がオープン。はじめのうちは‘WORK LOUNGE’でコワーカー的な利用をしていたが、ある時、キッチンでイベントをしていた人々に声をかけられレコード部に参加することに。やがてレコード部の‘BUSHITSU’をシェアさせてもらうことになったという。
「社員を雇うことになり『オフィスが必要』と考えたけれど、普通のシェアスペースでは面白みに欠ける。そんな話をレコード部の部長さんに話したところ、今のような形になったんです」


ちなみに株式会社セオ商事に入社した今井さんは哲学科出身だったことから「哲学部」を運営するようになった。 ‘BUKATSUDO’に出入りする中でも特にモノ好きな人たちが集まり毎回ハチャメチャな議論を展開しているという。
新たな流行が日々交錯する東京メインストリームとは距離を置き制作活動に専念できる利点と、仕事と遊びの垣根を取り払った‘BUKATSUDO’特有の開放的な雰囲気。瀬尾さんはそこに居合わせた人々と徐々に繋がり、2018年末に「ニューQ」という雑誌を刊行した。この「新しい問いを考える哲学カルチャーマガジン」は、‘BUKATSUDO’だからこそ生まれた、ユニークかつクリエイティブな産物なのだ。

「ウェブやSNSから申し込んでくれる方も多いですが、他の部活や‘BUSHITSU’を利用する方々も参加してくれます。『見えるようで見えない繋がり』が重なっている感じがとても面白い」
それまでの朝から夜に時間帯を移したという「ヨガ部」。毎回10人前後が参加するというレッスンを主宰するkanacoさんは、小さな娘さんを持つ、この地域の住民でもある。都会の片隅に佇む「大人の秘密基地」と呼ぶにふさわしい‘BUKATSUDO’について、彼女は意外な事実を明かしてくれた。
「キッズ向けのバレエやリトミック教室もやっているから子どもたちも出入りしています。ちょっとした打ち合わせの間に娘の面倒を見てくれたりと、スタッフは小さな子どもたちにとても好意的。地元のママ友たちと『困ったときは‘BUKATSUDO’へ!』なんて話もよく出ます」
週末は人でごった返す観光地で、そこに暮らす人々がくつろげるスペースは決して多くはないはず。ヨガ部は月2回の開催だが、kanacoさんはこのところほぼ毎日、‘BUKATSUDO’に立ち寄っている。そんな中で地元コミュニティや近隣の住人との新たな繋がりも生まれていった。

1989年の横浜博覧会を節目に開発が本格化したみなとみらいだが、今後さらに横浜市の新市庁舎整備、京急グループ本社の移転、オアフ島の名門ホテル「ザ・カハラ・ホテル&リゾート」開業、神奈川大学みなとみらいキャンパスの開校などが相次ぎ、一方で大型マンションの建設により居住エリアが拡大、人口増に拍車がかかっている状況だ。
約1万人の居住者と約10万人の就業者は、会社や学校、家族といった従来の繋がりはあっても、それらが交差するような繋がりは見つけにくい。そんな彼らが‘BUKATSUDO’のような新たなカタチの“公民館”を通して繋がりを築いていけたとしたら、近い将来、これまで以上に知的で、もっと温かみのある都市が生まれるのではないだろうか。


都市から辺境へと渡り歩き、そこに暮らす人々と関わり合いながら体験した出来事を写真と文章で表現している。