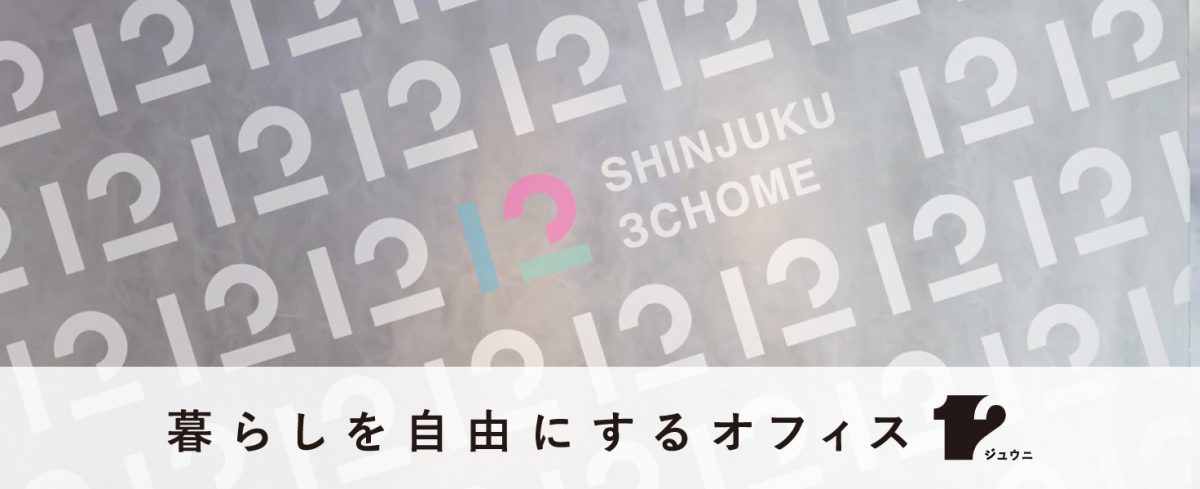山本 千織さんインタビュー
人と場に楽しさを届けるエンターテイナーなお弁当屋さん
北海道山越郡長万部町に、5人姉弟の長女として生まれる。短大卒業後に札幌の飲食店に勤務し、1998年から妹と共に定食屋「ごはんや はるや」を経営。2009年に上京し、2011年から代々木上原にある知り合いのバーを間借りして、手作り弁当『chioben』をスタート。彩り豊かで美味しいお弁当が、雑誌やテレビの撮影現場から口コミで広がり、現在は、パーティー会場などへのケータリングも行っている。著書『チオベン 見たことのない味 チオベンのお弁当』(マガジンハウス)。
色鮮やかな紫芋ボールはボリューム満点、意外な具材が驚きの春巻き、シャキシャキのキャロットラペや、出汁が美味しいホウレン草のお浸しは野菜をきちんと摂った満足感があって、タコ飯はコリコリ食感に山椒の実がアクセント。そんな、目にも舌にも美味しいお弁当『チオベン』を作っているのが、山本千織さん。ご近所コミュニティーの場だったという実家の料理体験や、多様な人々が行き交う飲食店での経験など、誰もが楽しくなるお弁当が生まれるまでのお話を聞きました。
さまざまな人が行き交う場所にあった「料理」
—『チオベン』の料理人として日々、料理をしている山本さんですが、最初に料理をした記憶は何歳のころですか?
9歳くらいかな。私の実家は北海道の田舎で海が近いのですが、海が荒れた後の浜には、貝や魚が大量に上がります。それを近所の人が持ってきてくれて、祖母がどんどん捌いていくんです。その捌いた魚の身をすり鉢に入れて、私が両膝ですり鉢を抱えてすり身をつくっていたのが、最初の料理の記憶です。祖母がすり身を丸めて、片っ端から揚げて大量の揚げかまぼこをつくっていました。
実家は建設の会社をやっていて、家の隣に会社がありました。母親が家と会社を行き来しながら仕事と料理をしていて、従業員のみなさんと一緒にごはんを食べるような家でした。
—いろんな人が出入りする家だったのですね。
お祭りなど地域のイベントごとがあると、近所の人たちも家に集まって、みんなで料理をして食べるのが普通でした。広い家で、真ん中に大黒柱のある居間があって、そこが近所の集会所みたいになっていました。
実家の台所は、最近の家では考えられないくらいに広かったです。薪ストーブの上に鍋を置けるスペースがあって、ストーブの前で調理ができるようになっていました。台所の壁が食器棚になっていて、裏口は魚を干す場所があるとても贅沢なつくりの台所でした。
—その広い台所で、日々たくさんの料理が作られていたのですね。日常的に料理のお手伝いをしていたのですか?
お正月や桃の節句、お彼岸など、行事ごとにおせち料理や赤飯などの行事食も作る家だったので、母親がとても忙しかったんです。私は、姉妹4人、男1人の5人姉弟の長女で、上の2人姉妹でよく母親を手伝って料理をしていました。生地を丸める、包む、パン粉をつける、揚げるなど、流れ作業でできる餃子やコロッケは、姉妹で横並びになって同じ作業を延々と繰り返して、大量のおかずを作っていた記憶があります。

—大きな台所で、小さな子どもたちがお手伝いをしている光景が目に浮かびます。結果的に料理人になったということは、その頃から料理が好きだったのですか?
子どもですから、手伝いをするよりは遊びに行きたいと思っていました。大学生のころまでは、仕事で料理をするとは思っていませんでした。
大学を卒業してすぐに料理人と結婚して、彼が札幌で始めた定食屋を手伝っていました。でも、何年か経ったころ彼にほかにやりたいことができて、店を出てしまって。私は手伝いをしていただけで料理人は彼だったし、お店をどうしようかと思ったんですが、ふと中華鍋に蝦片(エビ)を入れて振ってみたら、鍋のふちを蝦片が「くるん」と回って、鍋底に着地したんです。その時、心配して駆けつけてくれた友達と「すごい!料理をやっていけるかもしれない!」と盛り上がりまして(笑)、女友達を集めてお店を続けることにしたんです。
—中華鍋で蝦片が回ったことで料理をする決意がつくなんて、ポジティブですね!
そうですね、若かったからかもしれません(笑)。今では、女性だけでカフェをやるのも当たり前になっていますが、当時は、20代の女の子たちがやっている定食屋は珍しくて、近所のおじさんたちにすごくうけて、たくさんの人が常連になってくれました。
でも、いつの間にかとても忙しくなって、へとへとに疲れてしまいました。30歳を目前にして、これからの自分を見直していたときに、お店を始めるために物件を探している友人夫婦がいて、良いタイミングだと思って、彼らにお店を譲りました。
—大学を卒業してから料理の道を走ってきて、30歳を前に一旦停止したのですね。
ずっと旅行に行きたいと思っていたので、数ヶ月は海外旅行に行きました。旅行から帰ったあとは、飲食系の仕事をしている友達から声を掛けてもらって、何軒か知り合いのお店を手伝っていました。その後、妹が夫婦でやっていた「ごはんや はるや」という定食屋で手伝ってほしいと言われ、それから12年間働きました。
—長く働いたお店を離れて東京に行くことになったきっかけは、何だったのですか?
12年やって40歳を超えたときに、その先の予想ができたんです。とても良い店だったけれど、その先も同じ場所で料理を続けることに気持ちが高揚しなくなっていました。そんなとき、東京の友達から、お店をつくるから手伝ってほしいと連絡があったんです。ちょうど良い機会だと思って、上京しました。


「人との縁」から生まれ、広がっていった『チオベン』
—東京に来て、どんなお店を手伝っていたのですか?
代々木上原にあるブータン料理店で手伝いをすることになりました。その店は夜だけの営業だったので、「空いているお昼の時間に北海道でやっていた定食を出したい」と言ったら、「やっていいよ」と言われたので、ランチ定食を出していました。
ランチを食べに来たお客さんに「ブータン料理って食べやすいんだね」と言われて、「いえ、これは日本食です」と説明しながらやっていました(笑)。
—ブータン料理屋で日本食が出てきたら、たしかにお客さんは混乱しますね(笑)。
でもそのあと、ブータンから料理人が来ることになって、私は辞めないといけなくなったんです。そうしたら、ブータン料理店の向かいにあったバーの店長が、「営業していない昼の間、場所を貸すよ」と言ってくれたんです。ただ、バーなので料理を出す食器が無くて、バーの店長が「弁当箱で出したら?」と提案してくれたんです。
—それが『チオベン』の始まりなのですね!
そうなんです。『チオベン』には仕切りが無いとよく言われるのですが、もともとワンプレートランチとしてお弁当箱を使っていたからなんです。
そうしてランチを始めたものの、全然知られていないから、毎日数人の友達が来てくれるだけでした。みんなその場で食べていくから、弁当箱の蓋ばかりが残っていました(笑)。

—そんな始まりだった『チオベン』が、どのようにして雑誌やテレビの撮影現場で人気のお弁当になっていったのですか?
そのバーの近所で働いている雑誌の編集者がランチを食べに来てくれて、「現場にお弁当を持ってきてほしい」と言われたのが最初でした。
代々木上原は、フリーランスの編集者やライター、カメラマン、アパレル関係の人が多く住んでいる土地柄なので、「あの店でお弁当をやっている」と口コミで広がって、お弁当を撮影現場に仕出しする機会が少しずつ増えていきました。撮影現場でお弁当を食べた人が、「次はこっちの現場にも持ってきて」と依頼してくれるようになって、注文が増えていきました。
『チオベン』という名前は、当時のお客様が私の名前「千織」と「弁当」を組み合わせて言い始めたものでした。
—料理人になったことも、東京で『チオベン』を始めたことも、人の縁が大きなきっかけだったのですね。
いろんな出会いに恵まれ、まわりの方々に助けられてきました。『チオベン』も、最初に注文してくれたお客様たちが発信力の強い方たちだったので、名前を広めてもらえました。
ただ、もしも失敗したらすぐに悪い評判が立って終わってしまうかもしれないという緊張感は、常に持っています。逆に、きちんとやれば良い反応があることも分かったので、反応をちゃんと見て、改善が必要ならすぐに改善に取り組んで…その繰り返しです。
もともと雑誌や本が好きだったので、それらが生まれる現場も好きになりました。たくさんの人でひとつのものをつくっていく雰囲気が好きだし、現場でみなさんが一生懸命に働いている姿を見るのも好きなんです。撮影現場は、たくさんの刺激がもらえる、とても好きな場所です。

—現在、『チオベン』作りのアトリエとしているこの一軒家も、素敵な場所ですね。
注文数が増えてきて、前の場所のキッチンは狭かったので引っ越したんです。代々木上原から広がったご縁なので、同じエリアで物件を探して、この平屋建ての一軒家を見つけました。
—庭がキッチンの借景になっていて、木漏れ日が入ってくる、とても気持ちのいいアトリエです。アトリエづくりでこだわったのはどんなことですか?
まずこだわったのは、窓から見える広い庭でした。「YAECA HOME STORE」の庭も手掛けたグラフィックデザイナーの黒田益朗さんにお願いして、「適度な鬱蒼感」をテーマに庭をつくってもらいました。
あとは、お弁当箱をたくさん並べられる広い作業台のあるキッチンと、そのキッチンを舞台のように眺められるように、半階上がった部屋の襖をガラスに変更しました。元からあった古いキッチンもそのまま使っています。自分が出せる資金の範囲内で、理想のキッチンがつくれたと思います。


食べる人と場への気遣いを盛り込んだ、色鮮やかなお弁当
—『チオベン』はその色彩の鮮やかさが特徴的で、「見たことのないお弁当」として評判です。お弁当づくりで影響を受けているものごとはありますか?
アートやデザインの本を見るのが好きです。ギャラリーにもよく行きますね。アートの「へんてこさ」というか、かっこよく言えばアートスピリッツのようなものは、お弁当づくりで見習っている部分があります。
常に新しいことをやるように心掛けるとか、型にはまっていない面白さを求めるとか、気持ち良さのなかにほんの少し引っ掛かりを感じさせるものづくりとか。アートという、ありきたりではないものを見ることからの影響はあります。あと、作品が出来上がるまでにかけてきたアーティストの膨大な時間を考えて、自分も頑張ろうと思ったりしますね。
—『チオベン』をみていると「型にはまらないお弁当づくり」を楽しんでいることが伝わってきます。意外な食材や調味料との組み合わせも『チオベン』の特徴ですが、味付け面で工夫していることはありますか?
『チオベン』のお弁当には決まったメニューがなくて、ボリュームに応じた価格だけが決まっています。メニューは基本的にお任せで作らせてもらっていますが、お客さんには「肉を入れてほしい」とか「魚がいい」とか、「こうしてほしい」となるべく具体的に言ってもらうようにしています。
例えば、『チオベン』のお弁当はヘルシーとよく言われるんですが、お客様のなかにはヘルシーを求めていない人もいます。ある現場に行ったとき、そこで働いている男性スタッフたちを見て、「彼らはこのお弁当であと半日も働くのか…!」と気がついて、その後は揚げ物もたっぷり入れるようにしたり。お客さんのオーダーになるべく応えることと、現場での気づきを取り入れることが、『チオベン』の原動力になっています。
ー『チオベン』は、撮影現場やミーティングなど、人が集まる場で食べられることが多いと思うのですが、「みんなで食べるお弁当」として意識していることはありますか?
具体的なオーダーをもらうようにしているとは言いましたが、基本的には「何が入っているかお楽しみ」というお弁当にしています。『チオベン』のお客様はロケ弁に慣れている人も多いので、飽きないように肉、魚の組み合わせを変えたものを数種類作ることもあります。それだと、それぞれが食べたいものを選ぶ楽しみがあるし、現場のみんなに会話も生まれると思うんです。

—食べる人のシチュエーションまで考えて作っているのですね。大家族のお母さんのような気遣いを感じます。
ただ、作る側が大変になるまでやるのはダメだと思っているので、今の体制でできる範囲の気遣いをする、と決めています。無理をすると作ることが楽しくなくなるし、スタッフが飽きてしまうとクオリティが下がります。
『チオベン』のお弁当のおかずは固形です。作るときは1個ずつ作るから大変なのですが、固形だと数字で管理できるから、余らせたり、足りなくなったりすることを防ぐことができます。無駄を省くことと、スタッフが安心して楽しく料理できる環境づくりも意識しています。
—毎日の料理を楽しくするコツや、お弁当づくりのアドバイスはありますか?
頑張りすぎると辛くなるので、一所懸命にやりすぎないということでしょうか。例え間違えても、「これはこれでいい感じかも」と思うくらいでいいと思います。私も、粉ふるいが面倒くさくなったら、粉をふるわずにボウルに入れてしまうときもありますし(笑)。料理が嫌いで合っていないと思う人も、何か面白いと感じる部分を見つけて、自分が楽しんでやることが大切だと思います。
お弁当づくりのコツについては、時間が経っても水気が出ないものを入れると良いです。ただ、水気が出ないように調理しようと思うと、調味料の量が増えたり味が濃くなりがちなので、『チオベン』では各材料の下味をしっかり付けてから調理するようにしています。
—「手作りのお弁当が茶色になりがち」という声をよく聞きますが、色鮮やかな『チオベン』のお弁当は、そんな方のお弁当作りの参考にもなりそうです。
私としては「茶色くなったお弁当も愛する」くらいの気持ちでお弁当作りをしていいと思いますが、あらかじめ色のあるおかずをいくつか用意しておくと便利です。『チオベン』では、紫芋で作ったボールやキャロットラペなどをよく使っています。ベースは茶色くても、色のあるものをひとつ入れるだけで見栄えが良くなります。彩り用にきれいな色の野菜を見つけるのも楽しいですよ。私は、スーパーマーケットをぐるぐる回って、色のきれいな珍しい野菜を見つけるのが好きです。


多様なものとの出会いと許容がある世界が好き
ー毎日たくさんのお弁当の予約が入っていて多忙な山本さんですが、リフレッシュの方法は何ですか?
旅行が好きなので、長く休めるときは海外旅行に行きます。毎年、年末は海外旅行に行くのですが、去年はカンボジアに行きました。アジアは近いし、食事が美味しくて好きです。アジア旅行は、食べる楽しみがあります。
—旅先で出会った印象的な食べ物はありますか?
最近だと、ラオスで食べたバナナフラワーのつぼみですね。ミョウガのような形をしていて、たけのこに近い味でシャクシャクした食感なんです。それを細かく刻んで、豚肉と和えたサラダがとても美味しかったです。世界を見回すと、本当にいろいろな食材があるなと感じます。
—海外旅行に行く時間が取れないときは、どんなふうにリフレッシュしているのですか?
仕事の合間に本を読むのが、息抜きになっています。よく読むのは随筆家の武田百合子さん(※1)の作品で、強く気高い気性を持ちながらも、「こんな私ですが、何とかやらせてもらっています」みたいな、チャーミングに自虐を盛り込んでくる感じが好きなんです。向田邦子(※2)さんの文章にも同じような雰囲気を感じます。
ふたりとも、世間一般が思う「幸せ」は手に入れなかったかもしれないけれど、好きなことに向き合って、意見を持って主張して、自分の仕事は根性を入れてやっていた。そんな彼女たちの生き方に惹かれるんです。

—武田百合子さんや向田邦子さんのようなしなやかな強さは、山本さんにも感じます。
ありがとうございます。彼女たちが生きた昭和の始まりのころは、実は今よりもずっと、多様な人が生きやすい時代だったのかなと思います。武田百合子さんの本には、そういう時代の空気を感じさせる話があって、それがとてもいいんです。
私が子どものころに、近所に耳が聴こえなくて、発音が困難なおばあさんがいたんです。それでも私に話しかけてくれるのですが、「あーあーあー」としか聞こえなくて、子どもだから障害を理解していなくて萎縮してしまっていたんです。ある時、その現場に母親が出てきて、「あーあーあー!」って大声でそのおばあさんと会話をしていて(笑)。言葉じゃない言葉で話しているのにそれが通じ合っているんです。武田百合子さんの本を読むと、そういう、子どものころに抱いた懐かしい感覚を思い出します。
—カッコイイお母さんですね!
私たち5人姉弟を育てながら会社の手伝いもして、さらに近所の人たちや仲間が集まる場を仕切るような母親だったので、とにかくサービス精神が旺盛なんだと思います。今も、『チオベン』のお弁当づくりを手伝いにもきてくれるんですよ。
「楽しさを届けたい」が仕事のモチベーション
—『チオベン』で、これからやってみたいことはありますか?
フリーズドライをやってみたいんです。『チオベン』の1500円のお弁当にはスープが付いているのですが、どれだけ熱くして運んでも現場では常温になってしまうので、それをどうにかしたくて。フリーズドライなら、お湯入れるだけで温かいスープを飲んでもらえると思いつきました。
—食べる人と、そのシチュエーションを考えてフリーズドライにチャレンジする。まさに、お母様のサービス精神を受け継いでいるように感じます。
もちろん食べる人のことは考えていますが、それよりも、「フリーズドライをやったらうけるだろうな」という考えが先でした(笑)。私たちの作ったお弁当を食べるときに、フリーズドライのスープに喜んでもらったり、「スープが温かいね」という会話が生まれたら、うれしいなと思って。
—「うけること」が仕事のモチベーションとは、すてきです。そうしたところも、『チオベン』のファンが増えている理由なのかもしれません。
例えばこういう取材を受けるときも、きちんと話をしながら面白い話もすると、「あの雑誌に出ていたね」とか、「楽しい記事だったね」というふうに、まわりが反応してくれやすいと思うんです。そうすると、まだ『チオベン』を知らない人にも、私たちのお弁当を食べてもらうきっかけが生まれやすくなるんじゃないかなと思うんです。
—お弁当だけでなく、取材も「うけること」が狙いなのですね(笑)。
母親から譲り受けたサービス精神が一番現れているのは、この部分かもしれません(笑)。
※1 武田百合子:随筆家。1925年生まれ。作家である武田泰淳の妻で、夫の死後に、一緒に過ごした富士山荘での生活を描いた『富士日記』を出版。日常生活を鋭い視点で淡々と描いた文体で処女作ながら高い評価を受け、田村俊子賞を受賞した。1993年死去。
※2 向田邦子:脚本家・エッセイスト・小説家。1929年生まれ。1980年に連作『花の名前』『かわうそ』『犬小屋』で第83回直木賞受賞。料理が得意で、執筆活動をしながら「女性が一人でも気軽に寄れるお店」をテーマに妹と小料理屋を営んでいた。1981年死去。

山本 千織さんのお気に入り
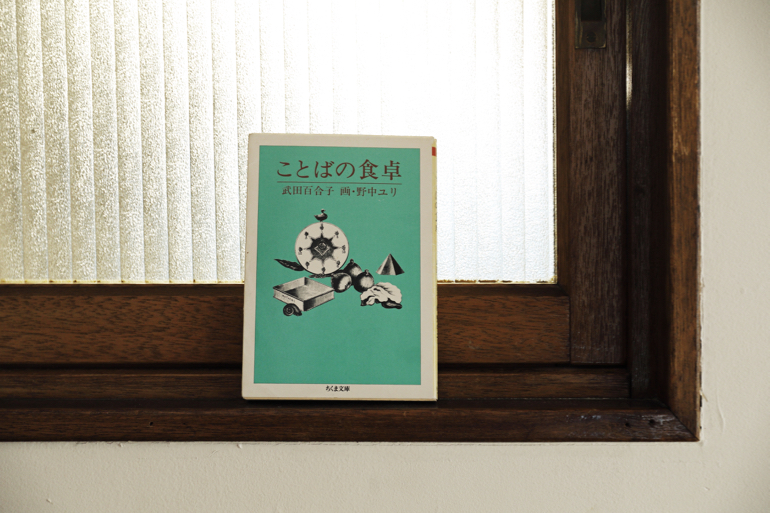
何度も読み返す、料理の合間の癒し
随筆家・武田百合子の代表作のひとつ。著者独特の感性で描かれた、食べ物がテーマの14篇の随筆集。ユーモラスな語り口のなかにさりげない風刺が織り交ぜられた文体で、没後も多くのファンに親しまれている。山本さんは、特に本作の昭和時代の風景が垣間見える文章が好きで、料理の合間の息抜き時間や移動中に読んでいるという。
『ことばの食卓』
武田百合子・著/野中ユリ・絵(ちくま文庫)定価:本体640円+税

フードプロセッサーがないと生きていけない!山本さんの強力な相棒
お弁当作りで余ったおかずや材料は、全て粉砕してペースト状にして、調味料やスープに変化させるのが『チオベン』流。食品の無駄を省くために活躍するのが、このふたつのフードプロセッサーだという。まったりと、とろみのある仕上げにしたい場合は『バイタミックス』で、基本的な粉砕で使うのは『クイジナート』と、用途でこのふたつを使い分けている。
左:クイジナート「リトルプロプラス フードプロセッサー」LPP-2JW(オープン価格)
右:バイタミックス「TNC5200」(オープン価格)
※写真の商品と現行販売品は異なる場合があります

代々木上原の美味しいもの好きが集まる小さなバー
上京してからほとんどの時間を代々木上原周辺で過ごしてきた山本さん。このエリアには、美味しいもの好きの人たちが集まっているという。友達と飲みに行くのが大好きだという山本さんが通うのが、知人の店でもある『Bar à vin Maison Cinquantecinq』。5人も入れば満員になる店内は、お酒好きが集う濃密な空間。
「Bar à vin Maison Cinquantecinq」(バーアヴァンメゾンサンカントサンク)
東京都渋谷区西原3-5-1 1F
TEL 03-5454-5631
営業時間18:00~翌00:30(ラストオーダー)
定休日:月2回不定休 チャージ300円