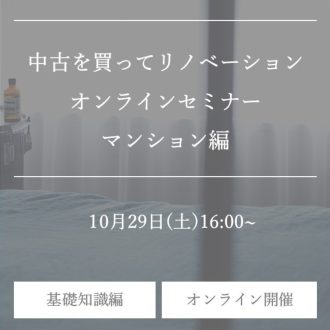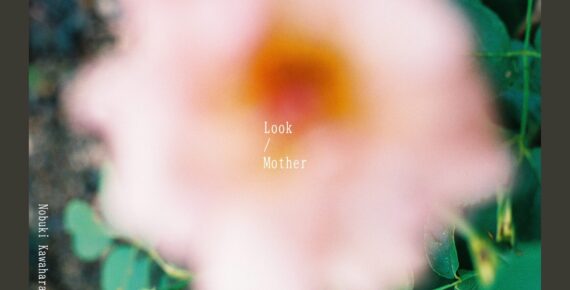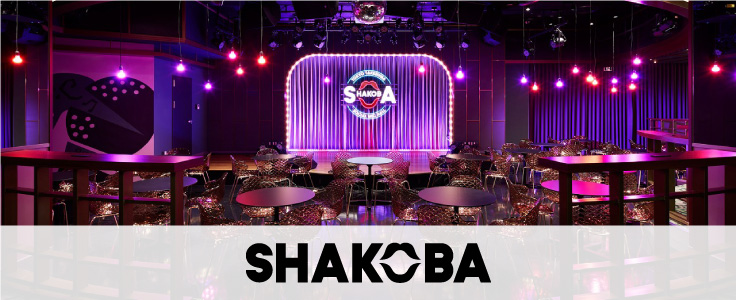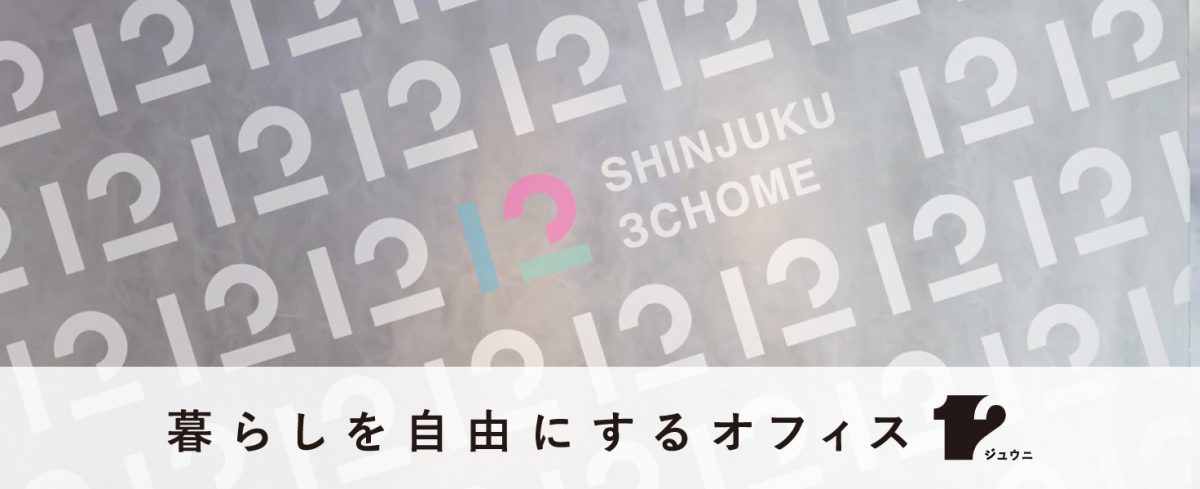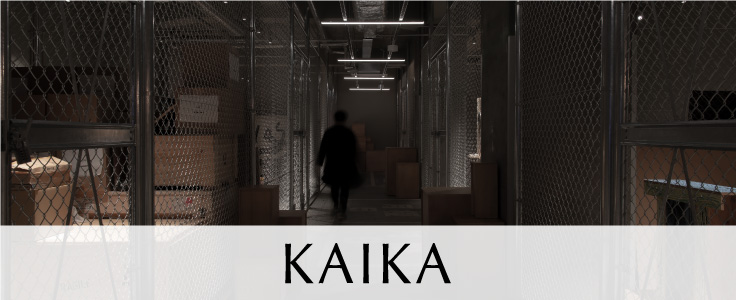Overview Coffee矢崎智也さんインタビュー
美味しいコーヒーが教えてくれる、環境と暮らしの良い関係

1984年生まれ、北海道出身。2015年にFuglen Coffee Roastersでセールスマネージャーとしてコーヒー業界でのキャリアをスタートし、2022年にOverview Coffee Japanに加入。セールス・マーケティングを中心に、ホールセールパートナーとのコミュニケーションや、新規開業サポートの他、ウェブサイトの記事のライティングや環境面での取り組みなど幅広く担当する。2025年4月から代表取締役に就任。プライベートでは100kmを超えるウルトラトレイルを主戦場に定期的に大会に出場する他、マラソン大会のディレクションや、ランニングメディアへの寄稿など走ること以外での表現の幅を広げている。
サステナビリティの次の視点として、いま各分野で注目されはじめているのが「リジェネレーション」です。連載『リジェネレーション<再生>の手触りをたずねて』では、実践者へのインタビューを通じて、その現在地を見ながら、私たちの暮らしにどう落とし込めるかを考えていきます。第1回のゲストは、Overview Coffee代表の矢崎智也さんです。
『Overview Coffee』はコーヒーを栽培方法から見つめ直し、リジェネラティブ・オーガニック農法で作られた豆を扱うスペシャルティコーヒーロースターです。土壌の再生と気候変動の問題解決へ寄与することをミッションに事業を進める矢崎さんの言葉は、環境負荷の低減と収益性の確保は両立できるということ、そして、環境にやさしい選択がより良い暮らしにつながることを教えてくれました。

気候変動を前に、コーヒーでできることがある
――Overview Coffeeは、2020年にアメリカで始まりました。設立のきっかけを教えてください。
Overview Coffeeの創始者は、アメリカ出身でプロスノーボーダーのアレックス・ヨーダーです。パタゴニアのスノーボードアンバサダーなどを務めていて、界隈で大きな影響力を持つ人です。彼が雪の減少を肌で感じたことから、気候変動に対して良いアクションをしたいと考えたのがOverview Coffeeの始まりです。ちょうど同じ頃に、パタゴニアは食から地球環境を改善するという理念のもとに、リジェネラティブ・オーガニック農法への転換を推進する食品事業「パタゴニア プロビジョンズ」を始めました。パタゴニアのアンバサダーとして動きを見ていたアレックスは、自身の体験と相まってOverview Coffee設立の原動力にしたようです。
――コーヒーに着目したのはなぜでしょう。
アレックスがコーヒー好きということと、世界的に流通量が多いので環境へのインパクトが大きいのです。アレックスは、コーヒーの魅力を「ritual(儀式、習慣)」と表現していました。淹れるときにセレモニーのような様式美があることや、人と人との距離を縮めるコミュニケーションツールとしての特徴があると言うんです。
――2021年に、広島県尾道市の瀬戸田にロースターをオープンしました。日本でOverview Coffeeが立ち上がった経緯は?
Overview Coffee日本の元代表を務めていた増田啓輔は、世の中や環境にとって良いことを前提にした焙煎所を作りたいと考えていました。その頃、アメリカではOverview Coffeeが立ち上がり、以前から知り合いだったアレックスと増田の思いが重なったんです。アレックスの人となりや考え方に共感し、環境への配慮が求められていく時代背景もあって、日本のOverview Coffeeが始まりました。

共感から広げる、コーヒーと環境の良い関係
――矢崎さんは、なぜOverview Coffeeに入ったのですか?
前職もコーヒー業界にいて、BtoBのセールスマネジメントを担当していました。当時はコーヒーの味が好きで入ったのですが、「自分の好きなことを通じて、環境に配慮した働き方をしたい」という気持ちが強くなって。コーヒーを扱いながら、気候変動の問題解決に寄与するというミッションを軸足に置いているOverview Coffeeに惹かれました。
――なぜ環境保全に興味を持ったのでしょう。
僕は10年以上トレイルランニングをしているのですが、自然の中で遊ぶほど、自然は大切な存在であると実感するんです。それに、自然災害で山道が崩れると、その場所は人の手を入れて保全しない限り地形が変わってしまう。自然の中に人が介入すると、そこから先はずっと人のケアが必要なんですね。トレランを通じて自然が崩れていく危機感を抱いたときに、「自分の仕事の重心が環境に寄り添ったものであれば、働きながらより良いインパクトを生み出せるのではないか」と考えました。
――Overview Coffeeに入って、環境に良いインパクトを残せていると実感したことは?
例えば、Overview Coffeeで使っている業務用のパッケージは100%生分解性の素材を採用しています。個人の選択としてプラスチックか紙かを選ぶ視点も大切ですが、仕事の中で環境に配慮した方法に改善するほうが、より大きな効果があります。
店舗では再生可能エネルギーを利用して、コンポストで生ごみを堆肥化し、フードマイレージの小さい食品を扱うなど、環境をより良くするための店のあり方を探っています。今は、日々の業務を通して環境をより良くしてきたいという気持ちが湧いています。

――そんな状況の中で、矢崎さんは2025年4月にOverview Coffee日本の代表に就任しました。環境保全と利益追求のバランスについて、日々葛藤することはありませんか。
迷うことはないです。環境が最優先というミッションベースで始まっているブランドなので、利益追求か環境保全かの2択なら環境を取る。パッケージの素材選びを例に挙げると、使える素材・避けたい素材・使えない素材がある中で、たとえ安価であってもミッションに反する素材は選択肢から外します。Overview Coffeeの理念上、使えないものは使わない、それだけです。ミッションが制約になって選ばざるを得ないとも言えますが、判断軸が明確だから決断は早いです。
ただし、コストが価格に反映される以上、なぜその価格なのかを伝える説明は欠かせません。Overview Coffeeが環境のためにどう良いのかを理解し、共感してもらう努力は続けていきます。その上で僕たちを選んでもらえるかどうかは、お客様やパートナーの判断次第です。できれば多くの人に共感してもらいたいし、僕自身も、環境配慮に取り組む人や企業に共感します。共感の輪を広げていくことで、環境への効果やインパクトに繋げていきたいと考えています。

――リジェネラティブ・オーガニック農法で作られたコーヒー豆の特徴を教えてください。
「これがリジェネラティブ・オーガニック農法の味」と断定するのは難しいんです。コーヒーの風味は、品種や産地の気候、栽培環境、焙煎のプロセスで大きく変わりますから。ただし、「どう作られるか」という点で大きな違いがあります。
リジェネラティブ・オーガニック認証は、パタゴニアなどが設立に関わった第三者認証機関「リジェネラティブ・オーガニック・アライアンス」が生産者を評価します。この認証には3つの大きな特徴があって、1つ目は土壌の再生性など農法そのものの評価です。剥き出しの農地を減らすカバークロップ(土壌改良のために休閑期や畑の空いた場所で栽培される作物)を導入することでCO2排出を抑えて、土中に炭素を固定する工夫をします。また、単一作物の連作で土地が痩せないように輪作するのも基本です。2つ目が動物福祉。動物福祉と環境の結びつきは想像しづらいかもしれませんが、放牧など動物の自然な行動を促すことで土壌が豊かになり、放牧する面積が広いほど良い循環で回る土壌が増えていきます。3つ目が労働者の公平性です。コーヒー農家への公正な賃金や安全な労働環境が確保されていないと認証が得られません。
リジェネラティブ・オーガニック認証のユニークな点は、監査の重複や煩雑な事務処理を避けるために、既存の認証制度をうまく取り入れている点にあります。「土壌の健康」はUSDAオーガニック認証をベースにしていますし、「動物福祉」はGlobal Animal Partnershipなどの認証を土台にしています。「労働者の公平性」については、フェアトレード認証や国際的な労働条約を基準にしていて、いずれの分野でも高い基準が求められます。
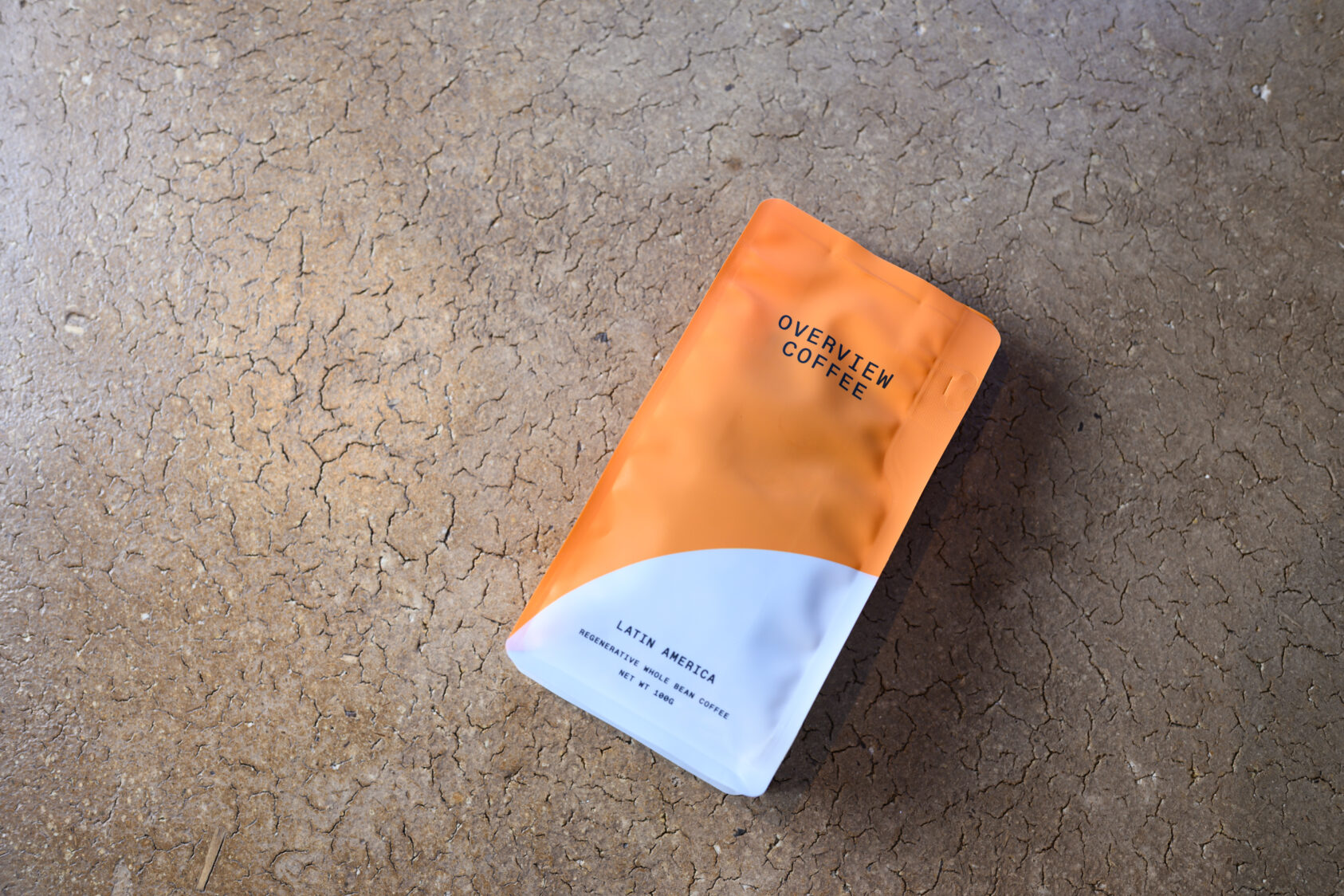
「好き」を大切にすることが、環境への優しい選択になる
――環境保全の意識は人によって温度差があります。環境問題を自分ごととして考えるには、どうしたらいいと思いますか?
個人的には、自然の中で遊ぶことを大切にしています。知識や理念ベースで仕事をするのも素敵ですが、誰かの心に響くのは意外とそこではない。僕の場合はトレランの気持ち良さがそうで、人よってはサーフィンかもしれませんが、言葉や理論がなくても「好きなことを大切にしている感覚」で結びついたときに、自然や環境への共感が広がっていくのではないでしょうか。この積み重ねが、結果的に環境にとって良い選択につながっていくと思います。

お店での体験もそうですね。「あの店で飲んだコーヒーは美味しかった」「心地良く過ごした」といった、訪れた人たちの経験の積み重ねに価値が生まれる。難しい文章でミッションやバリューを発信するよりも、こういった実体験のほうがよほど共感を呼ぶと思います。
――環境保全を優先するブランドで働きはじめてから、矢崎さん自身の暮らしに変化はありましたか?
もちろん僕も完璧ではないです。車に乗る頻度を減らしたり、ゴミの出にくい商品やパッケージ素材に配慮したものを選ぶなど、日常の選択でできることをしています。例えば、ランニングシューズを選ぶときは、環境への影響が1つの物差しです。カーボンフットプリントを明示するブランドが増えてきたし、プラスチック素材からサトウキビ由来の素材に切り替えるブランドもあって、そういう取り組みに共感して購入することもあります。Overview Coffeeの仕事で得た視点が、情報収集の範囲を広げているし、日常の買い物や行動に自然と反映されています。

最近良いなと思ったのは、アディダスのシューズのプライスタグです。一部のモデルに限った話かもしれませんが、以前はプラスチックだったのが麻紐に変わっていたんです。小さくて気づかれにくい部分ですが、取り付けの手間を考えると大きなチャレンジだと思います。グローバル企業が細部に配慮して環境保全に取り組んでいるのは、本当にいいなと感じました。
僕の仕事は、事業から生まれるすべてのものが環境と結びついていて、そこからどう良いインパクトを出していくかを考えることです。それが自分の暮らしの行動指針でもあるので、これからも環境にプラスの循環を作っていけたらいいと思っています。
認証豆も、小さな営みも。未来を作るコーヒーの選び方
――これからOverview Coffeeはどんな取り組みをしていきますか?
リジェネレーションという考えが社会に浸透するには、10年では足りないほど時間がかかる取り組みだと理解しています。それでも、その必要性は強く感じています。まずは、リジェネラティブ・オーガニック認証を取得しているコーヒー豆の消費を広げること。そのために、Overview Coffeeでの取り扱いを増やすことに注力していきます。
リジェネラティブ・オーガニックはまだまだ認知度が低いですが、オーガニック認証を取っているスペシャルティコーヒーのニーズは高まっていて、事業の選定基準として重視する事業者は増えている実感があります。生産者側も環境意識には差がありますが、僕たちがリジェネラティブ・オーガニック農法の豆を買い付けることでお互いに良い関係を築くことが、最初にたどり着くべきスタートラインだと考えています。
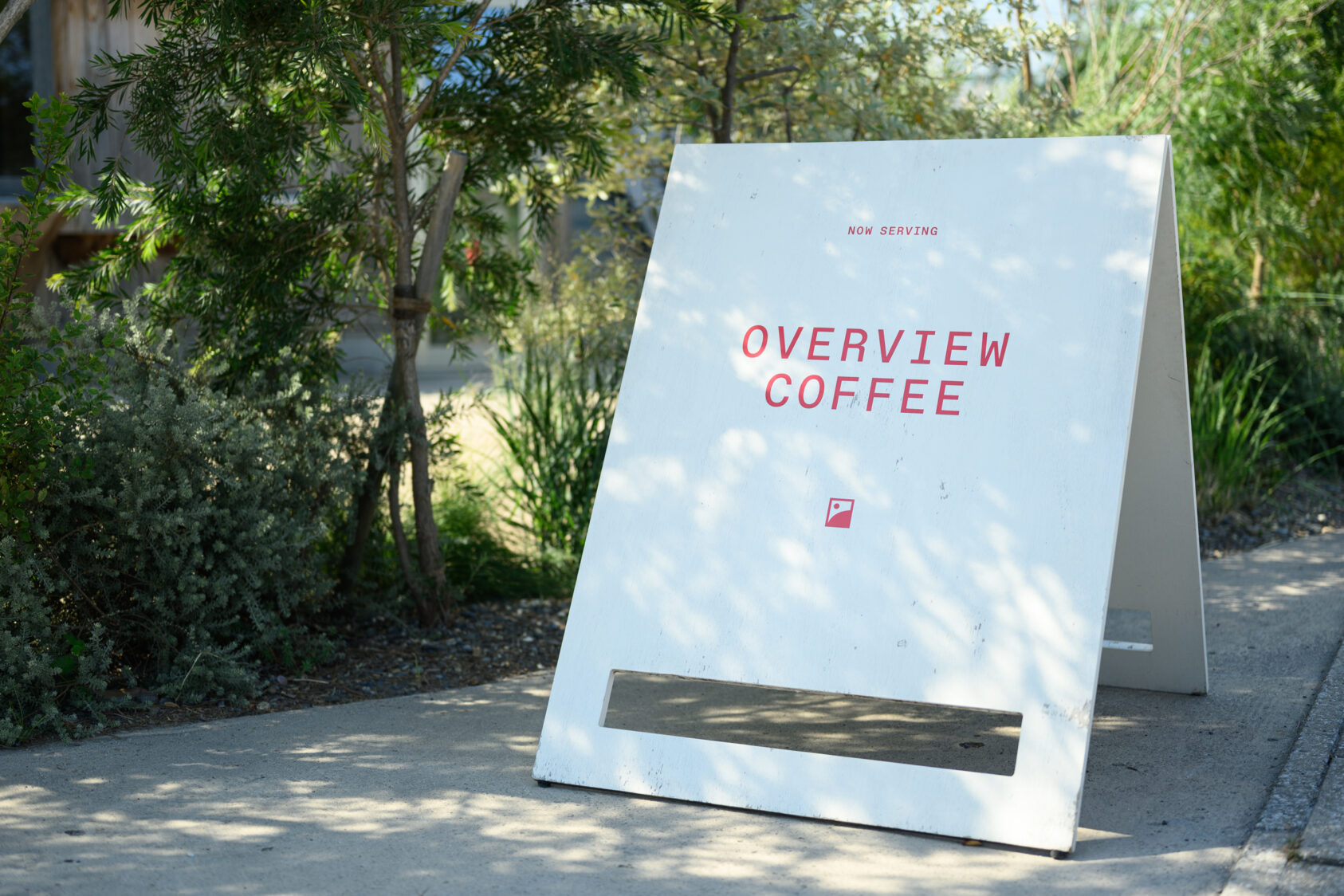
――リジェネラティブ・オーガニック農法のコーヒー豆を使うOverview Coffeeは、先駆的な取り組みをしているとも言えますね。
客観性という観点で認証制度の取得を重視していますが、同時に認証が全てではないことも理解しています。特に、コーヒーの場合は小規模生産者の割合が非常に高く、様々な理由で認証を取得するには高いハードルがあります。認証はなくとも環境面で先進的な取り組みをしている生産者は多くいますし、素晴らしいコーヒーを生産している生産者や団体も多くいます。2025年10月現在販売しているエルサルバドルのコーヒーは、カーボンニュートラルな農園運営と地域への還元を大切にした革新的な生産者です。今後は、認証制度に留まらず、環境面への取り組みに対して誠実な生産者を紹介できるように幅を広げていきたいです。