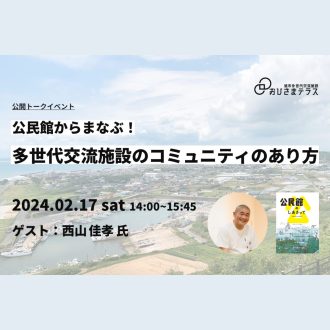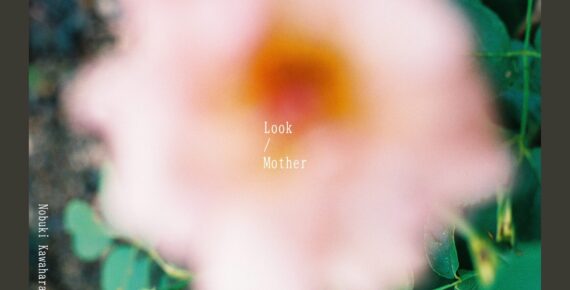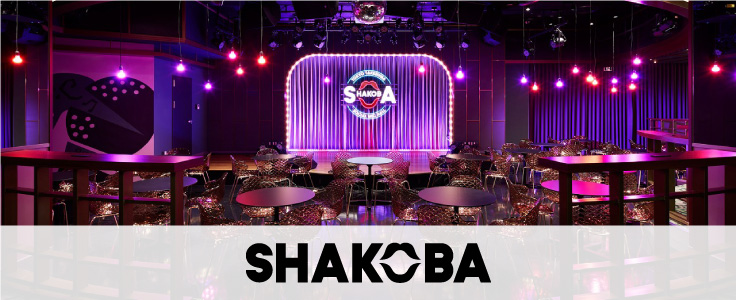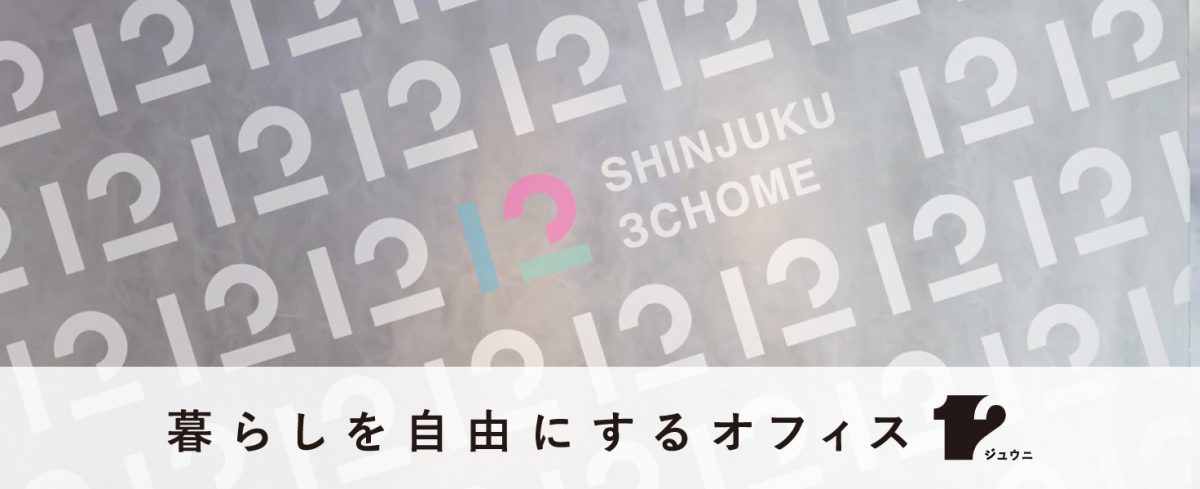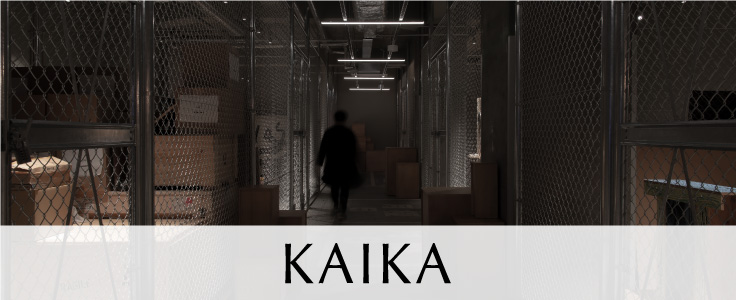自分流の使い方が見つかる、台所道具の選び方
さまざまな専門家にお話を聞いて、「リノベーション」や「住まい選びのコツ」をわかりやすく身につけるための「学ぶシリーズ」。今回お話を伺ったのは、「だいどこ道具ツチキリ」店主の土切敬子さん。ご自身が実際に使ってよかったと思う台所道具を扱う店を自宅の一角で営んでいます。昨年秋には新店舗「おちゃ道具ツチキリ」もオープン。台所道具の奥深い魅力や選び方、付き合い方のコツなど、ご自身の経験をもとにわかりやすく解説していただきました。
知れば知るほど面白い台所道具の魅力
台所道具は毎日使うし、そばに置いていつも目に入るものだから、デザインやかたちが好きであること、見た目が美しいとかカッコいいと感じられることも絶対に譲れないところです。でも、家具や雑貨と違って、道具として使う頻度がすごく高いという特徴があります。だから使いやすいものを選ぶことも、とても大切なポイント。よく言われることですが、デザインと機能のバランスが切実に求められるアイテムなんです。
そして、長く使ってみないと本当のよさがわからないというのが難しいところですね。最初はすごくいいと思っても、しばらく使っているうちに、自分には合っていないと感じることもあります。だから長年にわたり愛用できる道具を見つけたときは本当に嬉しい。この奥深さが台所道具の難しさであり、魅力でもあると私は考えています。
実際のところ、使ってみないと自分に合っているかどうかわからないものも多いですから、最初は手頃な価格のものを購入して、使って試してみることを繰り返していくしかないと思います。一定期間使ってみて、もう少しこだわりたいなと思ったら、少し価格の高いものに買い替えるのもいいですね。うちの店舗で扱っている台所道具は、私自身が実際に使ってみて、よいと思ったものを揃えています。1つのアイテムにつき、手頃なもの、少し高価なもの、その中間のものと、3種類の価格帯を用意することで、それぞれのニーズに合ったものを選んでもらえるようにしています。

台所道具選びは、自分を知ることから始まる
料理が好きな方でも、改めて自分の道具の使い方や道具に求める優先順位って、意外とわかっていないことも多いものです。だから、店舗にいらっしゃるお客さまとも「どんな風に使いますか?」「何を優先しますか?」と、背景にあるキッチンでの行動や生活スタイルを、会話しながらできるだけ詳細にお聞きして、その方の使い方や求める機能に合ったものをおすすめするようにしています。
例えば、ピーラーは機能やデザインはシンプルなものが好ましいけれど、「ジャガイモの芽取りがどうしてもほしい」という方もいます。そういう方には、芽取りがついたピーラーをおすすめします。

お話をお聞きしても、細かいところまではわからないので、使ってみたら合ってなかった、ということも起こります。
米用の木の計量カップの手触りがすごく気に入って購入された方が、数ヶ月後に「亀裂が入ってしまって、直せますか?」と来店されたことがありました。お話を聞くと、その方は米を測ったあとに、同じ計量カップで水も測るという使い方をしていたそうです。木の計量カップはそういう使い方を想定していないので、その方のスタイルには向いていなかったということになります。木の道具や器なども経年変化を楽しめる方であれば、普通の食器と同じように扱ってもいいですが、長い期間きれいに使いたいのであれば、使ったらすぐに洗って水気を拭くなど、それなりのお手入れが必要になります。

洗い物を減らしたいとか、時短でやりたいなどが優先順位として高ければ、それに合った道具がありますから、自分の使い方やほしい機能を知るというのは、台所道具の選び方としてとても重要なことです。
それから、毎日使う台所道具は、品質のよいものであっても経年劣化するものが多く、機能性が落ちてきたら買い替えることをおすすめします。私も先日10年ほど愛用していた陶器の生姜おろし器を、新しいものに買い替えたら、びっくりするくらい使い心地がよくて、まだまだ使えると思っていたけれど、実は摩耗していて、機能の低下に気づかず使っていたんですね。おかげで生姜をおろすのがすごく楽しくなりました。せっかくの道具だから、いい状態で使ってあげることを心がけると、料理が楽しくなると思います。
使い方は1つじゃない、自由な発想で組み合わせる楽しみ
私はもともと別々に使う道具を、組み合わせてオリジナルの使い方をするのが好きで、うちの店に足を運んでくれる方も、新しい組み合わせや使い方の発見を求めて来てくれることが多いです。
別々の道具のサイズがぴったりとはまった瞬間、これ以上ないくらいの喜びを感じます。代表的なものではティーポットとして使う耐熱ガラスサーバーに、サイズが合うドリッパーを組み合わせて、コーヒーサーバーとして使うという提案があります。私はこのガラスサーバーが大好きで、卵液を混ぜたり、水溶き片栗粉をつくるときなどにも使っています。しかし、残念なことにガラスサーバーは廃盤になってしまったので、器の作家さんに陶器のサーバーを依頼して、京都の辻和金網さんに金網のドリッパーを特注でつくってもらいました。

最近のお気に入りは、ガラスシャーレーに浅漬用の板、小さなトングを合わせた浅漬セットです。違うメーカーのものを組み合わせており、用途もオリジナルですが、ちょっと浅漬けをつくりたいときにすごく便利で、調理から冷蔵庫での保存までこれ1つでできて、そのまま食卓にも出せます。ガラスシャーレはメジャーなアイテムですが、浅漬用の板がぴったり合ったとき、使いどころがひらめきました。
毎朝のトーストを焼き立てのカリッとした状態で食べたいと思い見つけたのが、刺し身用の金網です。氷を下に敷いて刺し身を盛り付けるためのものですが、トーストにサイズがぴったり。毎朝お皿の上にこれを敷くだけで、トーストが水蒸気でフニャフニャになるストレスが皆無になりました。

ガラスサーバーを調理にも使うと言いましたが、1つで何役もこなす働き者の道具も大好きです。これも固定概念に縛られず、自分流の使い方を見つけていくことで、新しい使い方が生まれて、使う楽しみが増えていきます。
最近ではせいろが人気なのですが、手持ちの鍋やフライパンに合うステンレスのザルや蒸し器などを合わせて、蒸し料理を楽しむのも手軽でおすすめです。
おひつといえば曲げわっぱなど木製のものが人気ですが、陶器のおひつもおすすめ。うちで扱っている伊賀焼の陶器のおひつは、ふたの裏側に釉薬がかかっておらず、木製のおひつと同じように、水分調整をしてくれます。夜に余ったご飯を入れて冷蔵庫で保存して、朝そのまま電子レンジに入れて温め直せてとても便利。電子レンジで使えるということは、温野菜などの蒸し料理にも適していて、手軽でとても美味しくつくることができるのです。
日常を豊かにするお茶道具のすすめ
台所道具の店をはじめて、数がどんどん増えていったのがお茶関連の道具です。先に紹介したコーヒーサーバーとドリッパーを皮切りに、コーヒー、紅茶、日本茶、中国茶など、さまざまな道具を扱うようになり、昨年秋に新しい店「おちゃ道具ツチキリ」をオープンしました。お茶道具はそれぞれのジャンルで専門店があるほど奥が深いものですが、さまざまな種類のお茶の道具を集めて提案している店は少なく、男性のお客さまからもご好評をいただいています。お茶道具は料理をしない人も楽しむことができ、毎日使えるこだわりの道具を試してみたいけど、何から始めたらいいかわからないという人に、最初のアイテムとしてもおすすめできます。
お茶道具は用途に合った機能をもちながら、器としての魅力も楽しむことができます。朝のコーヒーから始まり、食後の日本茶、午後のティータイム、寝る前にはリラックスできるハーブティーなど、お茶は1日の中で何度も飲むものだから、そこで使う道具を1つずつこだわって選んでいくことで、想像以上に暮らしが豊かになります。
最近おすすめしているのは、耐久性が高く割れにくいトライタンという樹脂製の急須や、急須で入れたお茶と氷を入れて急冷できるポットなど、夏に活躍しそうなものです。
お茶道具についても台所道具と同様に、本来の用途とは異なる使い方や組み合わせの面白さをお伝えするようにしています。例えば、調味料などを入れるガラスの汁次を小さなティーポットとして使って、一口サイズのモールグラスとステンレストレーを組み合わせて、少しだけ特別なお茶の時間を演出できる「小さなティーセット」として提案しています。

すぐにできる工夫としては、急須やお茶碗、茶筒など日本茶の道具を茶びつに入れてまとめておくと使いやすく、ふたを開けて取り出すときに気持ちが引き締まる気がします。お客さまが来たときにも、心を込めて丁寧にお茶を淹れたくなります。何か1つこだわりのお茶道具を取り入れ、その道具を使うことで、1杯のお茶を入れる時間がとても贅沢なものになることをぜひ体験していただけると嬉しいです。

まとめ
毎日のように手に取る台所道具。土切さんのお話からは、道具選びを通して、自分の暮らし方や感性と向き合うことの大切さが伝わってきました。使い勝手や好きなデザインを考えることはもちろんですが、自分が「どんな時間を過ごしたいか」という生活のシーンをイメージすることで、ほしい道具が見えてくるのかもしれません。
なかでも、お茶道具は料理をあまりしない人にとっても、「まず1つ、お気に入りの道具を」と暮らしに取り入れる第一歩としてぴったり。1杯のお茶をいただく何気ないひとときが、丁寧で特別な時間に変わる。そんな体験をぜひ味わってみてはいかがでしょうか。
(ショップデータ)
◎だいどこ道具ツチキリ
東京都三鷹市井の頭5-2−28
OPEN:11:00 – 18:00 (定休日:火水曜日、木曜日は不定休)
https://keitoco.stores.jp
https://www.instagram.com/daidoko_tsuchikiri/
◎おちゃ道具ツチキリ
東京都三鷹市井の頭1-27-1
OPEN:月木金土日 12:00 – 19:00(定休日火水曜日、木曜日は不定休)
https://www.instagram.com/ocha_tsuchikiri/