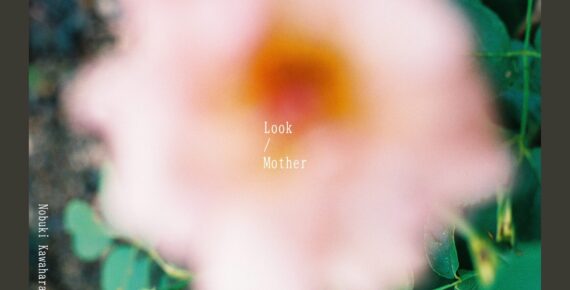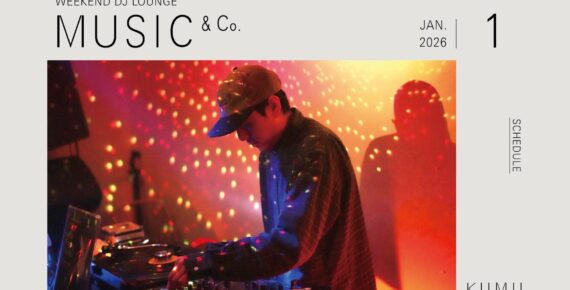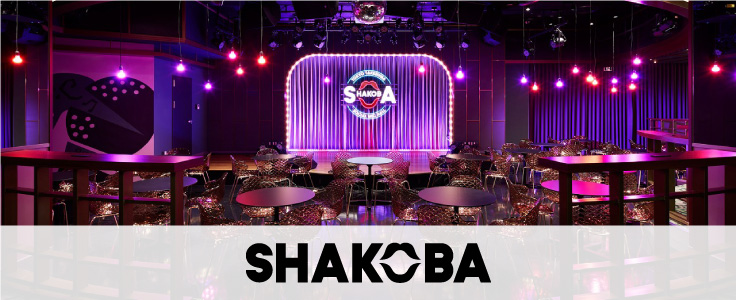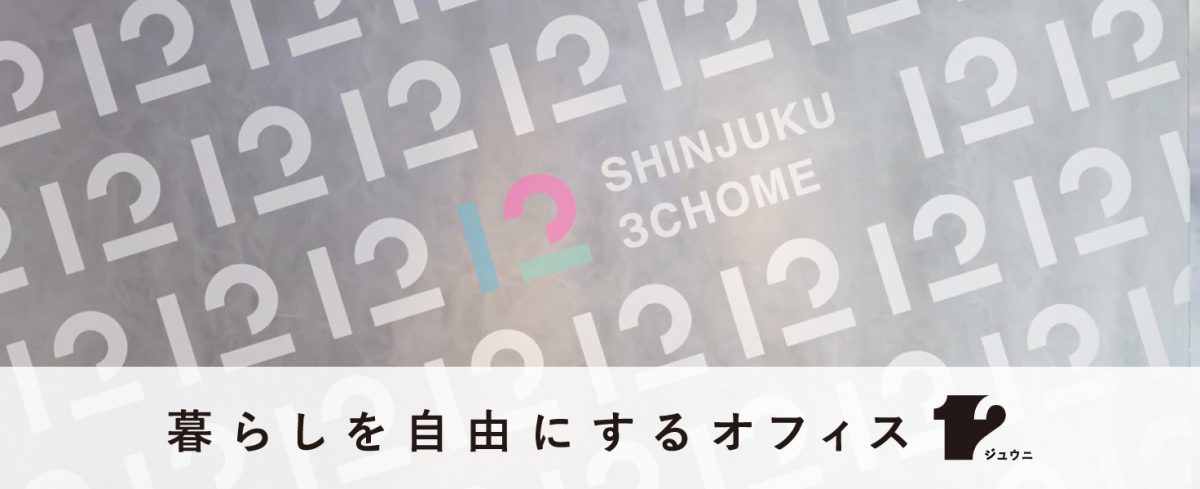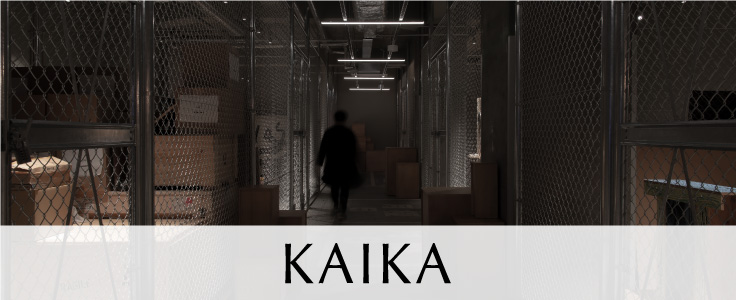佐々木類さんインタビュー
植物採集から始める、暮らしと地続きの作品づくり
1984年高知県生まれ。身近にある自然や生活環境にインスピレーションを得ながら、主に保存や記録が可能な素材であるガラスを用い、自分が存在する場所で知覚した「微かな懐かしさ」のありようを探求している。北欧やアメリカを中心に滞在制作招聘を受け、国内外の美術館で展示活動を行う。主な賞歴は、第33回Rakow Commission(2019年、コーニングガラス美術館/アメリカ)、富山ガラス大賞展2021大賞(富山市ガラス美術館)。ラトビア国立美術館(ラトビア)、金沢21世紀美術館など作品収蔵多数。近年の主な個展に「Subtle Intimacy : Here and There」(2023年、ポートランド日本庭園/アメリカ)、「雪の中の青」(2024年、アートコートギャラリー)、「不在の記憶」(2025年、WALL_alternative)がある。ニューヨークタイムズ紙や日本経済新聞などで作家特集掲載。2025年9月から開催される国際芸術祭「あいち2025」に参加。現在は、石川県にて制作。
2023年4月にリニューアルした「RAKURO 京都」は、新設したゲストラウンジ内にボタニカルラボを設置しました。植物の香りが漂う空間で目を引くのが、佐々木類さんによる『植物の記憶:北山中川の窓』です。みずから採集した植物をガラス板に封じ込めて焼成する作品には、植物の生きた痕跡が刻まれています。ここでは、植物採集が心身にもたらす効用や、国内外で活躍する佐々木さんの視点で地域性を紐解いて、豊かに暮らすヒントを探ります。
人と土地の記憶が、いつもの風景を特別にする

――『植物の記憶:北山中川の窓』制作で、心に残っていることを教えてください。
植物採集のために、北山杉の産地である京都の北山中川地区を訪れました。そこで文化的景観の研究をしている本間智希さんと山歩きをしながら、植物を採集したのが良い思い出です。1人で植物を採っていると“怪しい人”に見られることもあるのですが、今回は本間さんが一緒に歩いてくださったので、住民や仕事師など地域の方々とも話ができました。作品には、普段扱う小ぶりの植物に加えて、北山杉の名産地らしく大ぶりの杉を取り入れています。また、道端で目に留まった草や、お話をした方の畑に生えていた雑草など、その瞬間にその場所でしか集められなかった植物も加わりました。普段見ている自然でも、誰かの視点が加わることで特別な風景に変わるのだと実感しました。

――佐々木さんは植物と人の記憶のつながりについて、どのように考えていますか?
もし言葉が通じない地域に行ったとしても、植物は世界の共通言語になると思うんです。好き嫌いに関係なく、誰もが植物にまつわる記憶は持っていますよね。これは植物の特権だと思います。そして記憶は曖昧なもので、「どこで見たんだろう」と模索する。この模索の過程で生まれる会話から、徐々に記憶が鮮明になっていく時間も良いものだなと感じています。

ガラス板に植物を挟んで焼成した作品。養分を通わせた葉脈や土に張りめぐらされた根など、植物の生きた痕跡が灰になって永遠に保存される。素材:ガラス、植物(2023年3月25日に北山中川地区で採取)、LED、スチール枠
私の作品は植物を焼成して灰にするため色を持ちませんが、灰という曖昧さがいいと感じています。日本にしかない植物を使った作品を海外の方が見て、「子どもの頃に見たことがある」と話しているのを聞くと、灰という曖昧な状態だからこそ、誰でもアクセスできる普遍的な植物として立ち上がって、みなさんの想像力を引き出せているのかな、なんて考えています。
――普段は、どんなふうに植物採集をしているのでしょう。
いろんな方法で採っています。例えば、今までは採集した植物の名前は特に意識していなかったのですが、展示をすると必ず尋ねられるので、最近は採った植物をGoogleレンズで調べるようになりました。おもしろいのは、同じ植物でも地域によって呼び名が違うことがあるんです。『植物の記憶:北山中川の窓』の下部に入っているヒカゲノカズラは、京都では“ウサギノネドコ”と呼びますが、別の地域では“キツネノエリマキ”と呼ばれているそうです。私は、植物学的な正式名称というよりも、その土地の風土や文化に根ざした植物の特性を知りたいです。植物は衣食住に結びついていますから、名前を手がかりにしてその土地が持つ記憶の背景を知れるのがおもしろいのです。
五感を取り戻すために植物採集を始めた

――佐々木さんが、植物とガラスを使った作品をつくるようになったきっかけは?
私は留学を兼ねてアメリカに4年間滞在したのですが、帰国したときに、まるで五感をアメリカに置き忘れてきたような感覚がありました。過ごし慣れていたはずの実家の天井がやけに低く感じられたり、アメリカではいつも人工的な匂いに包まれていたのに対して、日本では雨やお日様の匂いといった自然に近い香りが日常にあって、その違いに敏感に反応していました。それで、五感を取り戻すためのセルフメディケーションとして植物採集をはじめました。自然に囲まれて過ごした子ども時代の記憶を呼び起こしながら、日記を書くような気持ちで毎日植物を集めたんです。
植物を採っていると通りがかった人が話しかけてくれて、そこから始まる会話を通じて土地の記憶が積み重なっていきます。その瞬間をタイムカプセルのように保存したいという思いから、植物とガラスを使った作品づくりを始めました。私の作品には泡が見えるのですが、それは植物が呼吸で取り込んだ空気やミネラルが焼成して灰になる過程で生まれる泡なんです。これは、身の回りにある空気や湿度など目に見えない環境を可視化できたらいいなという思いを具現化したものです。
アメリカにいた頃は日本のモノが懐かしくて、日本のお菓子のパッケージをガラスに閉じ込めて焼成する作品をつくっていました。ガラスを使った同じ技法の制作は20年以上続けていますが、植物をモチーフにするようになったのは、2012年に日本に帰国してからのことです。

――「五感を取り戻す」植物採集の方法を知りたいです。
最近は「五感を磨こう」「五感を鍛えよう」とよく言われますが、植物採集では意識しなくても五感が働くんです。棘が指に刺さる感触や、茎から出る液体の粘つきと匂い、根っこを抜くと出てくる虫を見ることで、心身が自然に動き出す。現代社会では多くのことが意図的に行われるけれど、植物採集をしているときは身体が環境に反応して五感が目覚めます。特別な採集方法はないので、直感で自由に採集してみるといいと思います。

――都心と田舎では、採集方法や感想が変わりそうですね。
そうですね。新宿で植物採集をしたことがありますが、都心の人ほど夢中になるんです。都心では土の性質もあって根っこから簡単にスポンと抜けるので、その感覚が楽しいようでした。没頭して採集するうちに、初対面の人同士が身の上話を始めるなど、不思議な現象も起こります。自然が、人をほぐしてくれているのかもしれません。一方で、地方の人は普段から自然を見慣れているので、「この植物の根っこは強そうだから抜き方を工夫しよう」と少し意図的になるシーンが見られます。
日常を離れるからこそ気づける、暮らしの奥行き

――佐々木さんは、様々な国で滞在制作をしています。海外で作品づくりをすることは、ご自身にどんな影響を与えていますか?
海外制作は、期間が1週間から数ヶ月までさまざまですが、自分のアトリエではない環境で制作をするので、不便や想定外のことがたくさん起こります。その不便さの中で、いつもならやらない方法を試すことができたり、思いがけない発見をすることも多い。効率は下がりますが、非日常の中でしか生まれない考え方や気づきがあるから、定期的に海外で制作をするようにしています。それに、日本語や日本文化を外から客観的に見られるのもいいですね。普段の暮らしの中で新しい気づきを得るには、一度外から眺めてみることが大切だと感じています。
――外から日本の文化を見て、どんな気づきがあるのでしょう。
日本は、暮らしのさまざまな場面で丁寧さがあると感じます。例えば紙の折り方ひとつとっても、折り紙・折形・手紙の折り方にはそれぞれ意味があって、相手への敬意が込められています。雨の呼び方にしても、日本にはたくさんの言葉があって、昔から自然に寄り添ってきた感性が表れていると思うんです。私は茶道を習っていますが、日本は古くからの文化をただ保存するだけでなくて、日々の暮らしの中で自然に受け継いでいくことを大切にしているように感じます。もちろん、ヨーロッパも古いものの保全には熱心ですが、日本は文化を敬いながら、現代生活に違和感なく取り入れているところに、美しさを感じます。

暮らしと作品づくりには境界線を引かない
――佐々木さんは、暮らしと制作のバランスで工夫していることはありますか?
基本的に、仕事とプライベートを分けないようにしています。私は天候や植物など、身の回りの環境にインスピレーションを受けながら制作をしています。どちらかに偏ってしまうと深く呼吸ができない感覚になって、精神的なバランスが崩れるんです。

どこに行っても自然はあるし、天候の影響を受けます。日常で目に入ってくるものが作品づくりの素になっているので、無意識のうちに仕事と暮らしが地続きになります。結局のところ、自分の興味と作品づくりは関連していて、興味のないことは暮らしの中でもしない。だから、仕事とプライベートは分けずにひと続きのものと捉えています。
――植物と丁寧に向き合う佐々木さんの姿勢から、暮らしそのものも満たされているのが伝わってきます。
日本人は昔から、植物と衣食住を深く結びつけながら暮らしてきました。そんな植物との関わり方は、今の暮らしにも活かせると思います。ストレスを感じたら、30分でも外に出て植物採集をしてみるといいです。植物を手に取るだけで、気持ちがほぐれていきますよ。

佐々木類さんの京都のお気に入りスポット
観光地ではない京都で、心ほどける散策を
RAKURO 京都で『植物の記憶:北山中川の窓』を見た後に、北山中川地区を訪れてみてほしいです。京都の有名な観光地ではありませんが、植生が美しいです。道端に生えている草花や丁寧に手入れされた北山杉を見て歩くだけで、リラックスできます。
北山中川地区へのアクセス|西日本JRバス(高雄京北線「周山」行)「京都駅前」→「北山中川」下車(約70分)
気軽に楽しむ京都のお茶時間
京都市役所前駅の近くにある『柳桜園茶舗』がおすすめです。京都のお茶屋といえば一保堂茶舗が有名で、観光客はそちらに行くことが多いと思いますが、柳桜園は気軽に立ち寄れて、お店の方との会話も楽しい。普段使いの煎茶からお茶会で使われる抹茶まで品揃えも豊富です。
歴史を感じながら歩ける古道へ
私は京都の山科に住んでいたことがありますが、自然豊かなエリアで、舗装されていない道が残っています。山科聖天から南禅寺に続く山道は、昔は多くの人が歩いたのだろうなと想像ができる古道です。車がなかった時代にタイムスリップした気分を味わえるお気に入りの場所です。