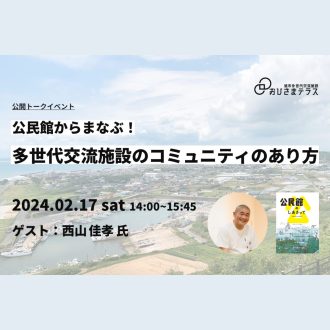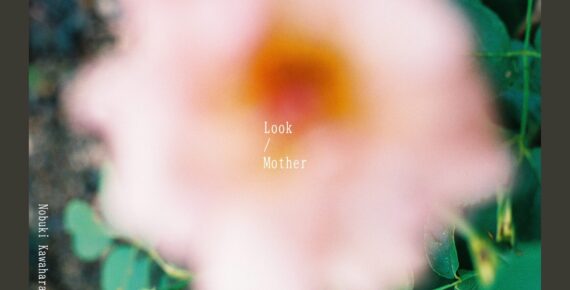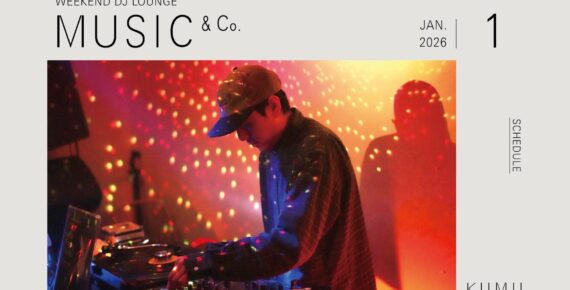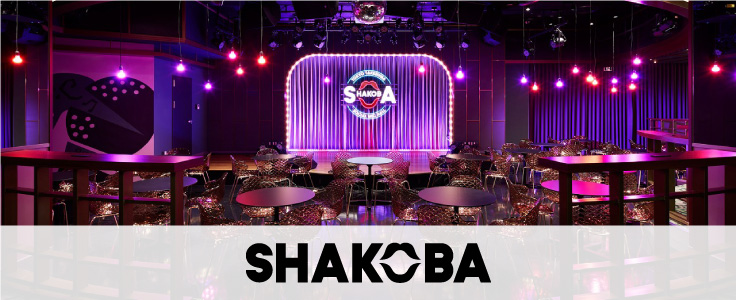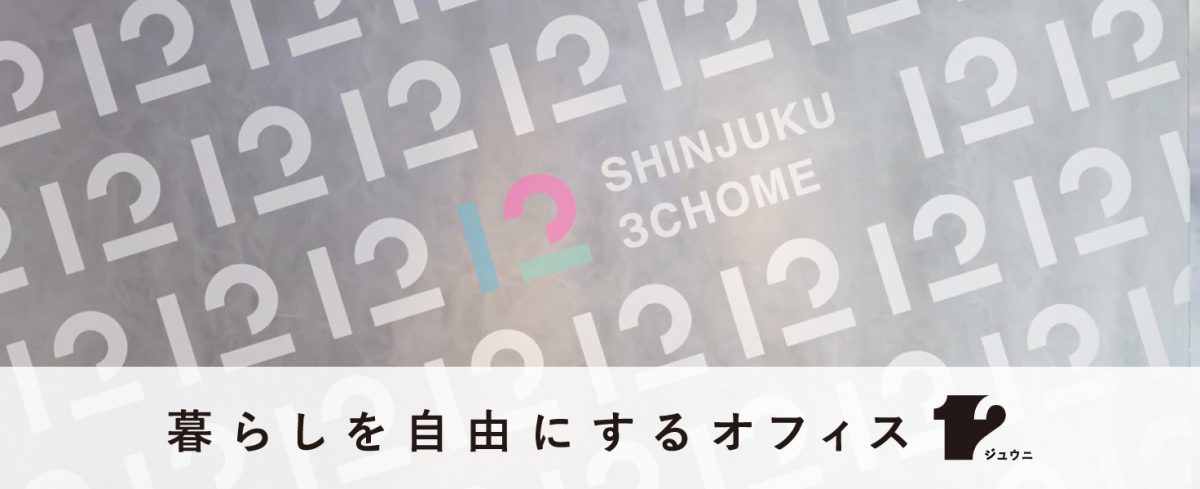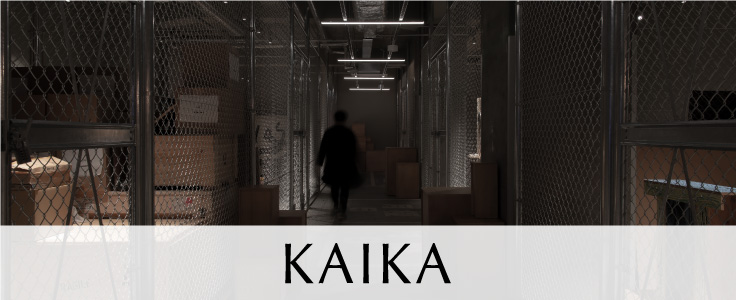自分らしいうつわの探し方を学んで、
心地よい食卓をつくる
さまざまな専門家に話を聞いて、リノベーション方法や住まい選びのコツ、暮らしを少し豊かにするヒントを得るための「学ぶシリーズ」。今回はテーブルコーディネーターの菅野有希⼦さんを招いて、うつわ選びのコツを学びます。新生活の準備をする中で、どんな食器をどれくらい揃えたらいいのか迷う方も多いのでは。ここでは菅野さんの体験も交えながら、長く使えて、統一感のあるテーブルスタイリングを叶えるうつわ選びを学んでいきます。
お皿選びのポイントは「一度で揃えないこと」「手の平サイズ」
私自身、ゼロからうつわを選ぼうとした時に、何をどれだけ買ったらいいのか全然わからなかったんです。料理のレシピはたくさんあるのに、食器の情報は少ないんですね。「とにかく必要だから買っちゃえ!」と勢いで買ったうつわが実際には使いにくかったり、見た目の可愛さだけで選んだうつわが浮いてしまって、結局手放した経験もあります。
うつわ選びに必要なのは、自分がつくる料理と食器の色・質感・サイズ・深さなどが合っているかどうかの判断です。ただ、新生活を始めたばかりの方はうつわ選びの勘どころがないと思うので、ここでは“選び方の基本のキ”をお伝えしていきます。

家族構成や料理をする頻度などの生活スタイルによって、必要なうつわは変わってきます。バリエーション豊かに料理をつくる方であれば様々な形のうつわを揃えたほうが良いですし、料理の回数が少ないならば最小限で十分です。いずれにしても、一気にすべてのうつわを揃えるのはやめましょう。まずは、誰でも必要な平皿と深皿かボウルを買ってみてください。暮らしていく中で足りないと感じたら、そのたびに足していけばいいんです。
お皿の選び方ですが、料理を盛る部分が手のひらサイズのものをおすすめします。手のひらサイズより大きな皿は、メイン料理を盛りつけたり、シェアする料理用と考えてください。意外と見落としがちなのは、お皿を買うときに平皿ばかり選んでしまうことです。平皿だけだと煮物やカレー、パスタなどを盛り付けにくくなるので、深さのバリエーションを考えて選ぶと良いでしょう。まずは、手のひらサイズの平皿と深皿(またはボウル)を一種類ずつ用意すれば、どんな料理を作っても活躍してくれるはずです。
チープに見えない茶碗とお椀の選び方
次は、ごはん茶碗とお椀の選び方です。茶碗は多種多様なデザインがあって派手なものも多いですが、個人的には「少し地味かな」と感じるくらいが食卓に馴染むと思います。うつわ選びは洋服選びに似ていて、結局のところ一番活躍するのは白いTシャツのようなシンプルなものです。あと、必ず茶碗を選ぶ必要はなくて、私は小さめの小鉢を茶碗に代用することもあります。

お椀は木製のものが多くてピンからキリまであるので、選び方が難しいです。木肌が見えるお椀にするなら、木目調のプラスチック製では少し残念感が出てしまうので、木製のものを選びましょう。漆器を買う時は、少し注意が必要です。プチプラで真っ赤な“漆器風”を見かけますが、あれはチープに見えすぎてしまいます。漆器のお椀を選ぶ時は、最低でも3,000円、できれば5,000円くらいの予算を用意すると良いものが見つかります。価格に見合う価値を感じられないという方は、まずはプチプラのお椀を試して、「どれくらい使うのか」「具だくさんの味噌汁が多いのか」など、自分の食卓のスタイルを観察してみてください。毎日使うことがわかったら、思い切って10,000円の漆器を選んでも満足感のある買い物になるはずです。
うつわ選びの基準は「テーブルに合わせること」
うつわの適性価格はそれぞれの金銭感覚次第なので難しいですが、参考までにお伝えすると、小さなうつわで1,000円台、手の平サイズで1,000〜3,000円台、大きなメイン皿で5,000円ぐらい出すと良いうつわが買えると思います。
うつわというと「作家もの」というイメージがあるかもしれません。ただ、作家はアーティストで、うつわは作品なので、自分の中でうつわ選びの基準を持っていないと選ぶのが難しいです。まずは、雑貨店やインテリアショップなど身近な店舗から探しはじめると良いと思います。選び方のポイントは、テーブルの色や質感に合うものを基準にすることです。白い天板のテーブルを使っている人と合板のテーブルの人では、合う食器が変わります。テーブルの雰囲気が似ていて、自分好みのスタイリングをしているInstagramアカウントや雑貨店、飲食店を参考にすることから始めるのはいかがでしょうか。

うつわの話をすると、「もう収納する場所がない」という声をよく聞きます。基本的なことですが、形状が安定していてスタッキングできるうつわを選ぶのが大切です。1年に数回しか使わないうつわで食器棚が埋まらないように、毎日使いながらハレの日も使いまわせるかどうかを見極めてください。
最近は、食器のスターターセットも販売されています。同色で5枚セットの皿やコップなどは一度に揃えられて便利ですが、食卓の美しさを考えると少し疑問です。同じお皿が並ぶ食卓は統一感を感じる一方で、マンネリ感が出てしまうんです。自分なりのうつわ選びの基準を定めるまでは長い道のりになるかもしれませんが、新生活だからといって慌てて買い揃えずに、一枚ずつ丁寧に選んでいくことをおすすめします。
“マンネリした食卓”を防ぐ色・形・質感の工夫
ここからは実例を出しながら、うつわのデザインと組み合わせについてアドバイスをしていきます。実際に使っていて便利なのは、どんな食材をのせてもきれいに見せてくれる白いうつわです。白いうつわといっても様々ですが、質感がマットなものや、焼き物の風合いが残っていて土の優しさを感じるものを選ぶと良いでしょう。写真でうつわの質感を見極めるのは難しいので、まずはお店で手に取って肉眼で自分好みの手触りを確認してみてください。

また、うつわの形を変えるのもおすすめです。うつわと言うと丸いものばかり選びがちですが、四角形や楕円形、八角皿を取り入れると、白いうつわが並んでいても食卓がおしゃれに見えます。
白の次に取り入れるうつわとして、意外と使えるのが黒いうつわです。個人的には、黒いうつわに料理を盛り付けると、お店のような雰囲気が出ると感じています。ただ、柄が入っていたりツヤツヤした質感の黒いうつわだと、高級感が出過ぎて日常づかいが難しいんですね。黒のうつわに関しては、無地でマットな質感のものを選ぶと良いでしょう。今回は、多くのショップで取り扱っていて買い求めやすい価格の「ハサミポーセリン」を用意しました。フラットなプレートは和食も洋食も合うし、使いやすいと思います。

知っておきたい、うつわの組み合わせの基本
最後に、うつわの組み合わせについてお話します。食卓に白と黒のうつわを並べても、違和感はありません。ただ、コントラストがありすぎて気になるという方は、白と黒の間をつなぐ馴染ませ色のうつわを取り入れると良いでしょう。

今回は、薄いグレーと黄色っぽいベージュのうつわを紹介します。ベージュのうつわは、土っぽい風合いのあるものを選ぶと良いです。触ったときにザラっとした手触りがあって、よく見るとツブツブの焼きムラが感じられるうつわは、のっぺりとして均質な印象の食卓から立体感のある食卓に格上げしてくれます。柄のうつわを選ぶのは難しいという方は、焼き物ならではの質感を活かして柄もの代わりにしてください。
組み合わせの一案として、うつわの素材を変える方法もあります。初めてでも取り入れやすいのは、ガラスのうつわです。陶器や磁器にはない透明感がありますし、選びやすくて失敗が少ないので、手軽に取り入れられると思います。サラダやマリネなど冷たい料理は、やっぱりガラスのうつわに盛り付けたほうが美味しそうに見えますよ。
今回は初めてうつわを揃える方に向けて、私が使いやすいと感じているアイテムや選び方をご紹介しました。ただ、テイストの好みは人それぞれです。ピンクやリボン柄などの可愛らしいデザインが好きな方もいれば、和食中心の方もいます。今回ご紹介したアイテムは必ずしも正解ではないので、うつわ選びの基本を理解したら、あとは自分の好みに合わせてチューニングしながら、うつわ選びを楽しんでみてください。

まとめ
今は、どこでも多様なうつわが揃います。そんな中で、今回は使いやすさや統一感のある食卓を実現するためのヒントを教えていただきました。最終的に100円の食器がしっくりくることもあれば、10,000円の漆器が自分に合うと気づくこともあるでしょう。大切なのは、「自分の暮らしを観察して、自分で選ぶ」というプロセスを楽しむことなのだと思います。