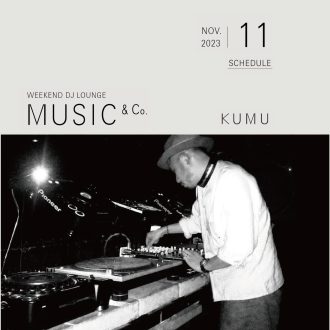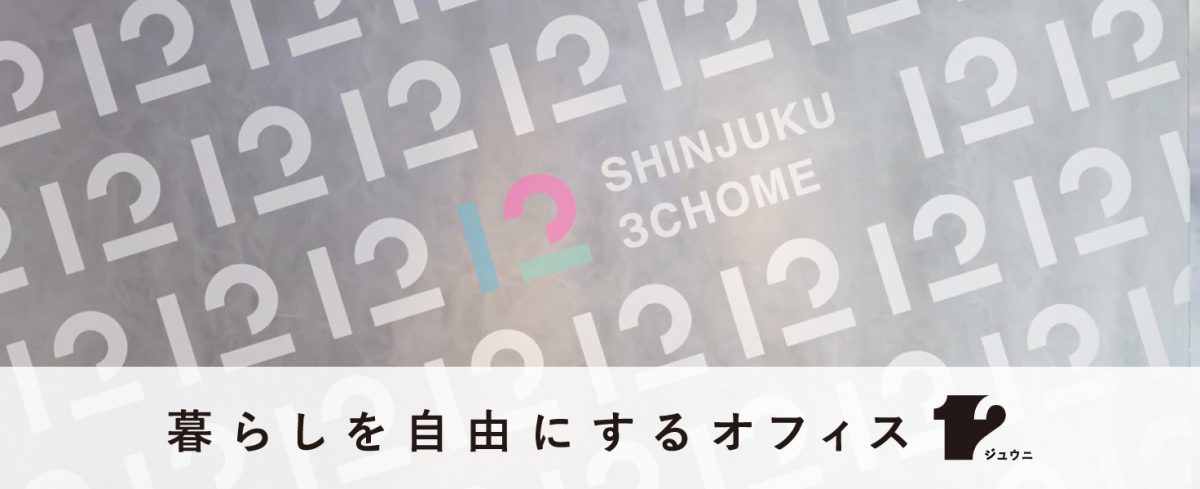mui Lab 大木和典さんインタビュー
情緒と余白を生み出すデジタルのあり方
ちょっと先、のくらし #01
のくらし編集長 石川が、多様な皆さんにちょっと先の未来をお聞きする「ちょっと先、のくらし」第一回。対談相手は、「穏やかなテクノロジー」をコンセプトに木のぬくもりを持ったスマートホームデバイス「mui ボード」を手がけている、mui Lab株式会社の大木和典さん。これからのデジタルと住まいと私たちの距離感についてお話を聞いてみました。
穏やかなテクノロジー
石川:まず、大木さんが手掛けるmui Labさんについてお聞きしてもいいですか?
大木さん(以下敬称略):mui Labは、新しく家族を持った方に向けたプロダクトを開発しています。例えば、私たちの手掛けるプロダクトmuiボードは、スマートホームの機能を持った室内のあらゆるスマートホームデバイスを一つにまとめるインターフェースです。家族と手書きや音声でのメッセージができたり、天気や日々のニュースを表示してくれることで、コミュニケーションのハブになってくれるんです。
石川:mui Labさんは、「穏やかなテクノロジー」というコンセプトを大事にされていますよね。少しこちらのお話を聞かせてください。
大木:はい。前提からお話しすると、現代社会には人口の4~5倍ものスマートフォンやスマートスクリーンなどのコンピューターがあると言われています。一人が4~5台のデバイスに囲まれているということは、常に処理しきれないほどの過剰な情報が人に降りかかるということになります。デバイスの普及に伴い、アテンション・エコノミーが広がり、企業の営利活動のために常に人の注意が盗まれる結果となっているのです。

石川:さまざまな通知が来続けたり、道を歩いていても色々なシステムに目を奪われたりしますよね。
大木:そう。今っておおよそコンピューターを使ったものに注意を引かれ続けているんです。これを改めてバランスを取るために「カームテクノロジー」という言葉がシリコンバレーを中心に提唱されはじめました。ですが、これはすごく西洋的だなと思うんですが「デバイスを静かにする」という、割と直接的な意味合いでしか捉えられていなかったんです。mui Labが提唱する「穏やかなテクノロジー」というのは、考え方は近いのですが、もっと自然に「空間の一部になれないか」という考え方です。環境の一部としてテクノロジーが機能したらいいなって。そもそも「mui」もそういった日本らしい調和の取れた自然なありさまを示す「無為自然」から名付けました。
石川:私たちリビタも「穏やかなテクノロジー」という考え方に共感して、協業することになったんですよね。muiボードに出会う以前から、私たちもスマートホームの技術には着目していましたし、素晴らしいとも思っていたんですが、なんとなくしっくりこなかったんです。muiボードは、そのデザインやたたずまいはもちろんですけど、私たちが提供したい価値観とすごく近いなと思っていました。
余白が生み出す情緒
大木:しっくりこなかったのは、スマートホームは、どうしても技術やスペックから語られすぎているからじゃないかと思います。muiボードもスペックから説明すると“Wi-Fiで繋がっていて、木を使っていて、タッチパネルが搭載されていて…”という事実の羅列になってしまうので、味気なくなってしまいます。どちらかというとmuiボードを使うと、どういう気持ちで過ごせるか、どんなふうに心が動くかということこそが大事なことなんですよね。そういう心のためにこそ、テクノロジーやデザインが機能すべきだと思うんですよ。

石川:私たちも大木さんとお話しすると、いつも心や情緒について共感しすぎて、打ち合わせが長くなりますよね(笑)。
大木:(笑)。リビタさんとお話する中で「テクノロジーっていうのはどこかしら殺伐としてるけど、muiからは情緒を感じる」といっていただけたのを覚えています。私たちのデバイスも、機能を詰め込みすぎず「余白」を大事に作っているんですが、リビタさんの手掛ける空間からもそれを感じるんですよね。
石川:「余白」ってすごい分かります。例えばリノベーションで言うと、お住まいになるお客様の思いや、ご自身の問いかけによって完成するような「余白」のあるデザインってあるんです。私たちがそういう余白を意識して作ることで初めて、その空間の主語がその部屋で暮らす住まい手さんになるんですよね。リビタもそういう余白はとても大事にしています。

大木:余白をデザインするのは難しい部分もありますよね。日本のビジネス潮流を見ると多くのシーンでコスト削減や費用対効果を求められてしまいます。それを推し進めると、いわゆる「余白」が生まれる余裕は無くなり、ニーズに合わせたツールしか生まれないですよね。
一方でユーザーはもっと幅広い選択肢を求めていたりもすると思います。導入することで、「こんなふうに暮らしが生活が変わるんだ!」といった、使う前には想像するのが難しいであろう我々のビジョンをどうやって提案していけるか、というのは常に考えていますね。
石川:特にスマートホームについては、まだまだ想像しきれていない部分は多いかもしれませんよね。実際私たちもお客様にご提案したこともあるんですが個人の利便性向上にどうやって寄与するの?って話になってしまうんですよね。
いい無駄が生まれるサイクル
大木:本当はスマートホームについてもスペックや費用対効果ではなくて、ライフスタイル全体で語ってあげることで、随分と印象が変わると思うんですよね。車から考えると分かりやすいと思うんですが、車って基本的には乗って走って移動できれば良いですよね。でも、どうしてあれだけ色々なメーカーや種類、カラーの選択肢があるかっていうと、多くの人に車に乗った体験があるからですよね。その体験と比較して「もっと自分らしい」だとか「もっと心地いい」っていう選択肢が広がったのだと思います。今はまだ、スマートホームそのものを体験していない人も多いので、色々な業種や業界と連携して体験を増やしていくことが大事なんだと思います。
石川:すごく分かりますね。一方で、余白や無駄を楽しむ方というのも増えていると思うんです。例えば、掃除機とかお掃除ロボットではなく、あえて手仕事で作られたほうきを選んでお掃除を楽しむ方もいらっしゃいますよね。効率面とか利便面から見たら、わずらわしいものだと思うんですけど体験や心からみると、選択肢の一つとしてすごく良いものです。スマートホームで省略した時間やコストをこういった感性や情緒を育む「いい無駄」みたいなものに変換するサイクルを考えるのはこれからの課題かなって思います。

繊細で強すぎないこと
石川:muiボードは、いい無駄を生み出すひとつのヒントになるかなって思います。
大木:muiボードは、ペンダントライトのような存在であればいいと思っています。ペンダントライトって、照明としてはすごく弱くてテーブルの周囲しか照らしません。でも、弱いことでもたらしてくれる効果やムードってありますよね。そういう繊細で強すぎないテクノロジーだからこそカイロスタイム(個人が持っている主観的な時間感覚)を優雅にしてくれると思うんです。
石川:先日、muiボードに詩を流してくれましたよね。あれは、もしかしたら一見無駄なことかもしれないけれど、見ていてすごく感動したんですよね。あくまで私たち人間が中心で、デジタルが少しだけ色をつけてくれるような。デジタルとの距離感ってこれくらいが理想だと思いました。
大木:僕はソファで寝てたら、勝手に歯を磨いてくれるとかそれくらいまでデジタル化は進んでもいいかなと思います(笑)。
石川:(笑)。

大木:歯磨きもそうですが、わずらわしいことが全て解決された後、私自身に何が残るのかというのには興味がありますね。自分自身の記憶すら体の外部システムに依存するような世界が訪れると、自分とそれ以外のしきい値が曖昧になって来ますよね。デジタルって、もっと自分ですとか本質的なことを突きつけてくるものだと思います。
石川:確かに、自分でも忘れてしまうような思い出を記憶してくれていたりします。もっと言うと、健康データなどの自分でも把握しきれない体の状態を自動で管理してくれるようになってきています。そうすると自分が「運動しよう!」とか「寝よう!」って言う行動する時のトリガーにはなり得ますよね。ある意味では、自分よりも自分を知ってくれているのはデジタルの特性なので、私たちの感情を取り出すきっかけとして機能するようになるのかなって思っています。

大木:記憶が蘇るような体験もできるでしょうし、デジタルはライフスタイルをより良い方向に拡張してくれますよね。同時に気をつけたいのは、人間は最新技術に熱狂しやすいものです。熱狂の中で本質を忘れてしまう、置いていってしまうというのは気をつけたいなって思います。人として技術の進化に適応するときに、幅広いリテラシーから考えるべきかなと思っていますね。基本的には、明るい未来になるって想像しています。
石川:パンデミック以降の想定外の中で、「テクノロジーは情緒・愛・倫理をなくしては成り立たない」ということに多くの人が気がつき始めたように思っていて、私も未来を明るく考えているんです。今日はありがとうございました。
大木:ありがとうございました。


2012年より新卒で入社したNISSHA株式会社の北米駐在員としてNISSHA USAシカゴ本社、ボストンオフィスへ勤務。2017年10月社内ベンチャーとして子会社mui Lab株式会社設立。2019年4月にMBOを行い独立し、2019年10月にはVC4社より総額約2億円の資金調達を実施。CES2019イノベーションアワード、Best of Kickstarter2019受賞。