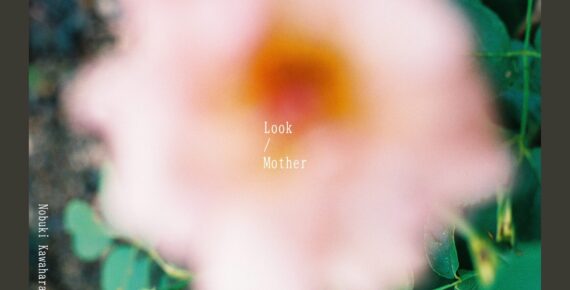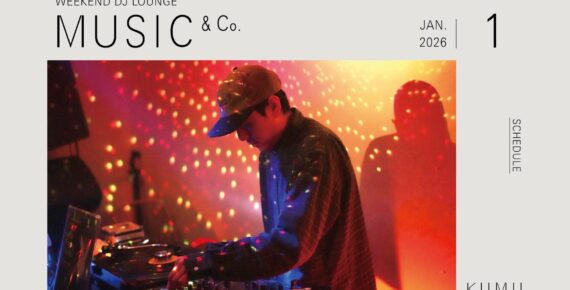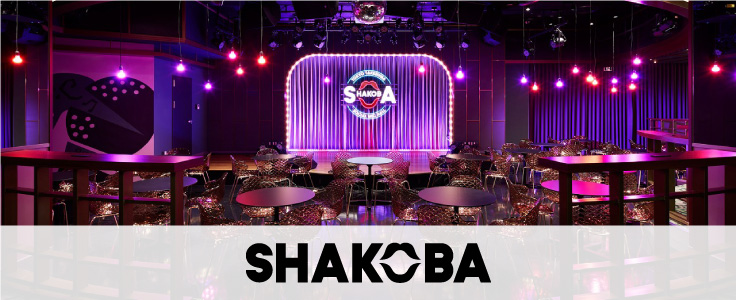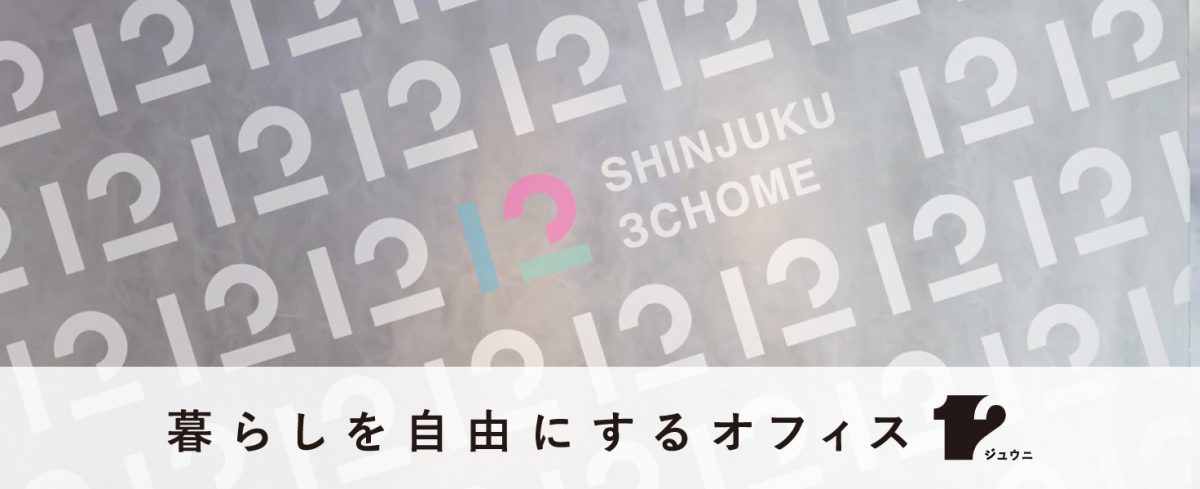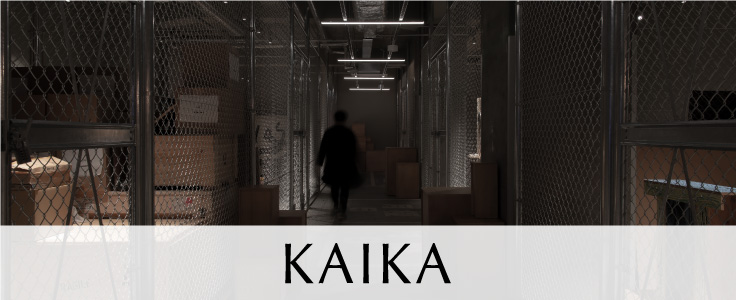「長く愛着を持って暮らす空間」をカタチに
初めての共創で生まれた、未来へつなぐリノベーション
リビタが手掛けるリノベーション済みマンションは、リビタがこれまで培ってきた住まいと暮らしに関する知識や経験を詰め込み、一つひとつの空間を丁寧に作り上げることで唯一無二の住まいを届けています。今回手掛けたリノベーション事例「東急ドエルプレステージ代々木公園」に関わったマルニ木工の山中洋さん、一級建築士事務所knofの永澤一輝さん、リビタの濵中亮輔に協業の背景や、「時をかける部屋」というコンセプトが生まれた過程を聞きました。「時間」をテーマに3社の知見が混ざり合った空間の魅力について、それぞれの視点から掘り下げていきます。
プロフィール
株式会社マルニ木工代表取締役社長 山中洋(写真中央)
1971年生まれ。明治大学商学部を卒業後に渡米。米国オールドドミニオン大学経営大学院を卒業後に帰国し、マルニ木工に入社。営業職を経て、外部デザイナーとの企画を推進し、2021年より現職。
一級建築士事務所knof 永澤一輝(写真右)
1984年生まれ。岐阜県大垣市出身。京都工芸繊維大学卒業、同大学院修士課程修了。2016年菊嶋かおりとともに一級建築士事務所knofを設立。
株式会社リビタ 濵中亮輔(写真左)
2018年にリビタに入社。プロジェクトマネージャーとしてリノベーションマンションの仕入・企画・販売を担当。
不動産と家具は、「時間」という軸で混ざり合う
――リビタとマルニ木工が協業することになった背景から教えてください。
株式会社リビタ 濵中亮輔(以下、濵中) リビタが展開するR100 tokyoのウェブマガジン『Curiosity』で、マルニ木工のリノベーション家具の取材をさせていただいたのがきっかけです。マルニ木工が提案するリノベーション家具はユーズド家具を修理するだけでなく、現代の暮らしに合わせて独自の視点でアップデートし、新たな価値を生み出す思想に基づいています。この考え方に触れて、住まいのリノベーションを手掛けるリビタとして深く共感しました。そして、「家具を修理して使い続ける文化を広めたい」というマルニ木工の思いがなかなか世の中に浸透しない課題を聞いて、ぜひ一緒に空間づくりをしましょうとお誘いしました。リノベーション空間とリノベーション家具は相性が良いと感じていましたし、社内で「マルニ木工と取り組むならどんな住戸だろう?」と話していたタイミングで、今回の物件の話が舞い込んできたんです。

株式会社マルニ木工代表取締役社長 山中洋さん(以下、山中) 私たちは家具づくりを96年間続けていますが、コロナ禍を契機に「数十年前に買った椅子をなおしてほしい」という声が多くなっていました。家具をなおしながら使うというニーズが高まっているのを痛感して、われわれ家具メーカーの重要な責務の一つは、製品に不具合があった時に適切な修理やメンテナンスを提供することだと感じていたんです。
それに、96年の歴史を重ねていると多くのアウトレット製品やリサイクル製品が出てきます。この製品にもう一手間を加えることで、現代の暮らしに合う価値を生み出せないかと考えました。過去にたくさんの家具を作ってきた私たちが担う役割を振り返った時に、リノベーション家具という発想が出てきたんです。この取り組みが、リビタさんの目に留まって取材していただいたという経緯です。

――そこに、設計パートナーとしてknofさんがジョインされたのですね。
濵中 マルニ木工さんとプロジェクトに取り組むパートナーとして適任だと思ったのが、knofさんでした。以前から、リビタとknofはさまざまなリノベーション物件を通して新たな取り組みを行ってきました。例えば、リビタが手掛けるリノベーションマンションシリーズ「mydot.(マイドット)」では、企画の軸となる思想を一緒に生み出して、これまでにない物件へと昇華させてきた経緯があります。「新しい協業のかたちに挑戦するならknofさんとやりたい」ということで依頼をさせていただきました。
一級建築士事務所knof 永澤一輝さん(以下、永澤) ありがたいです。リビタさんとマルニ木工さんが協業するという話を聞いた時に、何を軸にしたらいいのか悩みました。空間をきれいに仕上げてマルニの家具を置けばカッコよくはなると思いますが、もっと本質的なレベルで2社でしかできないコラボレーションのあり方を模索したいと考えました。そこで、マルニのことをもう一歩深く理解するために、茨城県坂東市と広島県広島市にあるマルニの工場を見に行ったんです。工場見学をするうちに、われわれの中では「マルニがやっていることについていこう」という気持ちになっていました。

濵中 リビタとしても、永澤さんとかなり近い感情になりましたね。
永澤 協業前は、マルニ木工さんといえばやはり深澤直人さんの「HIROSHIMA」やジャスパー・モリソンの椅子という印象でした。でも工場を見ていくうちに、著名なデザイナーに引っ張られて想像していたイメージだけではなくて、世界的な課題に正面から向き合った熱い取り組みを、現在進行形で行なわれていることがわかってきました。「いまマルニ木工の家具づくりの現場で起きていることを、今回のリノベーションの現場へ持ってこられないか」と考えたことがコンセプトの原点になりました。
山中 我々は木を使って家具を作る工場ですから、家具づくりしかできません。今回のプロジェクトが始まった当初は、こんな空間が出来上がるとは思ってもみませんでした。振り返ってみると、立ち位置はそれぞれ違いますが、ものを大切にするとか、なおして長く使うといった思想は3社が共通して持っていたと思います。
濵中 山中さんのおっしゃる通りです。リビタが作る物件の根底には、「長く愛着を持って暮らしてほしい」という思いがあります。3社それぞれの立場から「長く愛着を持って暮らすには?」というテーマを深掘りできたことが、今回のプロジェクトの質を高めたと感じています。
――コンセプトの「時をかける部屋」という言葉は、どのように生まれたのですか?
永澤 一般的には、まず不動産があり、建築があり、そこに家具が入るという階層構造があります。でもその考え方だと、不動産と家具はどうしても主従関係のようになってしまって今回のコラボレーションの形としてふさわしくないのではないか。改めてリビタさんとマルニ木工さんでしかつくり出せない価値とは何だろうと考えたとき、「時間」を軸に考えると腑に落ちる感じがしました。
リビタさんはリノベーションに力を入れている不動産会社で、築数十年の建物に新たな価値を付加して世の中に出す事業をしています。この行為自体、時間を扱っていると言ってもいい。
一方マルニ木工さんには、まず1928年創業という時間の積み重ねがあります。そして、樹齢100年の木材で家具をつくり、これから100年使われるために修理とアップサイクルを実践している。
2社とも、これまで流れた時間をリスペクトし、より良い未来を目指している。時間という軸で捉えると、不動産と家具は同じ地平で等価に考えられると思いました。
たとえば、新しい家具と古い家具の時間、家具になる前に木材が経てきた時間、それからこのマンションの躯体が経てきた時間、前の住人が大切に使っていた食器棚の時間、さらに、この代々木の地に流れてきた時間など、多様な時間を可視化し、触ることができ、楽しめるようにしたい。そしてその上にこれから住まう人々の時間を重ねていくことで、この先100年も愛されるような空間を目指したいという想いで「時をかける部屋」という言葉をコンセプトにしました。

山中 「家具の製造現場を建築現場に持ってくる」という発想から「時をかける部屋」という言葉を導き出すまでの思考プロセスをお聞きして、感情が揺さぶられましたね。コンセプトを噛み締めながら実際の空間に身を置いてみると、そこに込められたアイデアが深く心に響いてくる感覚があります。僕たちは家具メーカーなので、正直にいうとこれまで建築のことはあまり考えてきたことがありませんでした。
――今回のプロジェクトを通じて、ものづくりに対する視野が広がったということでしょうか?
山中 そうですね。例えば、人体に触れる時間が長い椅子は家具の中でもメインで、実際に椅子づくりは難しいです。その椅子のことを考える時に、大前提として座り心地の良さは大切ですが、我々の根底にある思いは「椅子は生活の道具であるべき」ということです。どんなデザイナーと取り組むにしても、主張しすぎずいろんな空間に馴染むことを大切にしているんですよね。逆に言えば、それぐらいの小さな視野でしか家具づくりをしてこなかったということです。今回は、もっと広い視野で空間づくりに取り組むことができたので、マルニ木工にとっても非常に意義深いプロジェクトになったと感じています。
部屋・家具を調和させるヒントは、工場にあった
――「時をかける部屋」を具体的に感じられるポイントを教えてください。
永澤 間取りを考えたとき、窓際のコンクリートの壁と柱は邪魔な存在に思えました。無くせるものなら無くしたいと。でもマルニ木工の工場で、昔の家具の塗装を丁寧に剥がして素材を現しにしてリノベーション家具として蘇らせる過程を見て、このコンクリートも丁寧に手入れをすれば触れたくなるような素材感が出せるのではないかと考えました。きれいに掃除をして、最終的には柔らかい質感が出て、この物件が経てきた時間を感じられる大きなチャームポイントになったと思います。

永澤 また、壁や天井は、マルニ木工さんの工場から出るウォールナットの木粉を練り込んだ左官材で仕上げています。この木粉左官材のアイデアのヒントになったのが、工場から出る廃材と物件が建っている場所の特性でした。ここは代々木エリアが紡いできた歴史と自然を感じられる場所であり、さらにこの部屋は地形的にもともと丘の斜面だったところを掘り込んだ位置にあります。この場所の時間を感じられるという意図で土(左官)という素材を選び、それをマルニの木と掛け合わせられないかと考えました。
濵中 家具の製造過程で出てくる木粉は、いわば家具の過去の姿です。それが壁や天井に塗り込められて、マルニ木工の家具と、住む人と一緒に新たな時を刻んでいく。この物語には情緒があって感動しますね。
山中 3社が集まって多様な知見が混ざり合ったことで、思いもよらないアイデアにたどり着きましたよね。アイデアが形になった空間に身を置くと、雰囲気と素材の質感が調和していてとても居心地の良い場所に仕上がったと感じます。
ものへの愛着と自然への敬意を育む空間

――ベルサイユチェアの前脚を扉の取っ手にしたり、端材をアート作品にするなど、「木」を尊重した取り組みもありますね。
山中 これには驚きましたね。工場では誰も見向きもしない木の端材に着目してアート作品にする発想は、われわれだけでは生まれなかったです。
永澤 マルニ木工の家具の美しさや耐久性を実現するためには、どうしても製作過程で大きめの端材が出てしまうという話を聞いたんです。空間のどこかで端材を活用できないかと思い、西舘朋央さんに声をかけて、マルニ木工の端材だからできることを考えていただきました。西舘さんが、特徴のある廃材の形をそのまま活かすことを尊重してくれて、木片をパズルのように組み合わせたアート作品ができあがりました。

永澤 寝室にある端材のレリーフは、マルニ木工さんが開発した高効率のフィンガージョイント技術を使っています。5種類の木材からできていて、それぞれが木として経てきた時間や場所がつなぎ合わされて1本の水平線をつくることで「いま、ここ」という現在性を表現できないかと考えました。
山中 フィンガージョイントとは、端材を縦横に接合して大きな板材にする技術のことです。業界内でもマニアックである技術に着目して、こんな作品ができたことに驚きました。

永澤 マルニ木工の家具に使われている木材や、技術を感じられるアートが空間にあることで、この空間と家具の結びつきをより高めています。
――「ものを大切にする」「なおして長く使う」という姿勢が、物件の魅力を高めましたね。
山中 家具の話でいうと、ヨーロッパの家具の歴史は400〜500年、一方で日本は約100年と家具を使ってきた歴史がまだまだ浅いです。ヨーロッパではセカンドサイクルショップが充実しているし、家具を親から子へ引き継ぐ文化が根付いていて、古い家具のマーケットもインフラが整っているんです。だからこそ、ヨーロッパから学ぶ部分はまだまだあると思っています。

山中 安価なものを購入して2〜3年で買い替える価値観も否定はしません。でも、僕たちは、ものを大切に扱うことで得られる本当の豊かさを多くの方に感じてもらえるような家具づくりを続けていきたいです。今回のような取り組みは1社ではできませんから、リビタさんとknofさんの力を借りながら僕たちの考え方が世の中に広がって、それに共感してくれる人が増えていくと嬉しいです。
濵中 我々もリノベーションという取り組みをする中で、ものに愛着を持って長く使っていくことの豊かさを広めていきたいと思っています。この物件にはたくさんの物語が詰まっていて、住まい手はその物語を語りたくなると思うし、そこに自分の暮らしを重ねながら味わい深く暮らせると思うんですよね。たとえ次の住まい手に引き継ぐとしても、この物件の物語はきっと色褪せない。今回は、普遍的な価値を持つ空間が提供できたと思っています。

あとがき
時の経過に敬意を払い、自然の恵みを受けた素材を感じながら、ものに愛着を持って暮らす豊かさを知る。そんな暮らし方ができる空間は、住まい手の価値観も変えるかもしれない……リノベーションの大きな可能性を感じるインタビューでした。何代も先の住まい手まで見据えた本質的で持続可能な住まいは、いずれ“愛すべきヴィンテージマンション”となって長く引き継がれていくのだと思います。
▼関連記事
マルニ木工コラム
生活者と共に歩むための本質的なものづくり。
【リビタ濵中亮輔×knof永澤一輝×マルニ木工 山中洋】記事もぜひご覧ください。
https://webshop.maruni.com/column/stories_vol78/
▼関連動画
プロモーションムービーをYouTubeにて配信しております。
【maruni × ReBITA のコラボ物件】—時をかける部屋‐