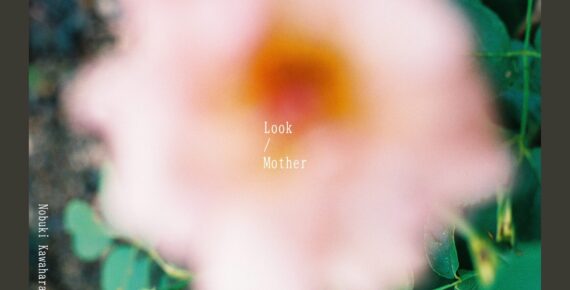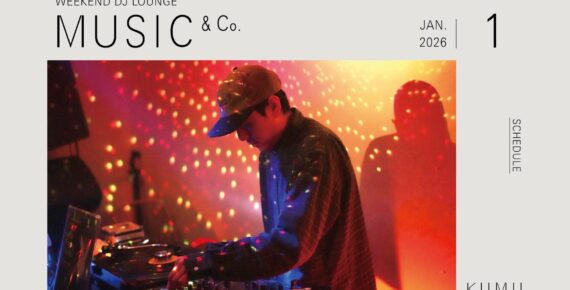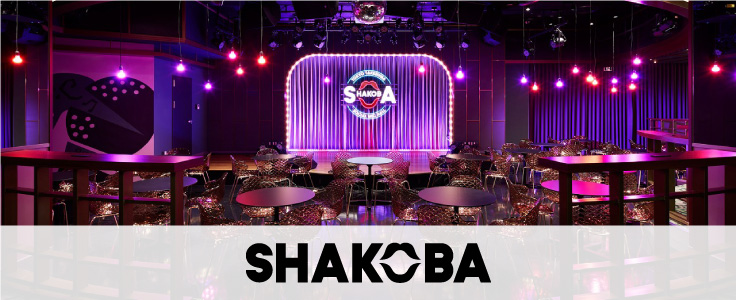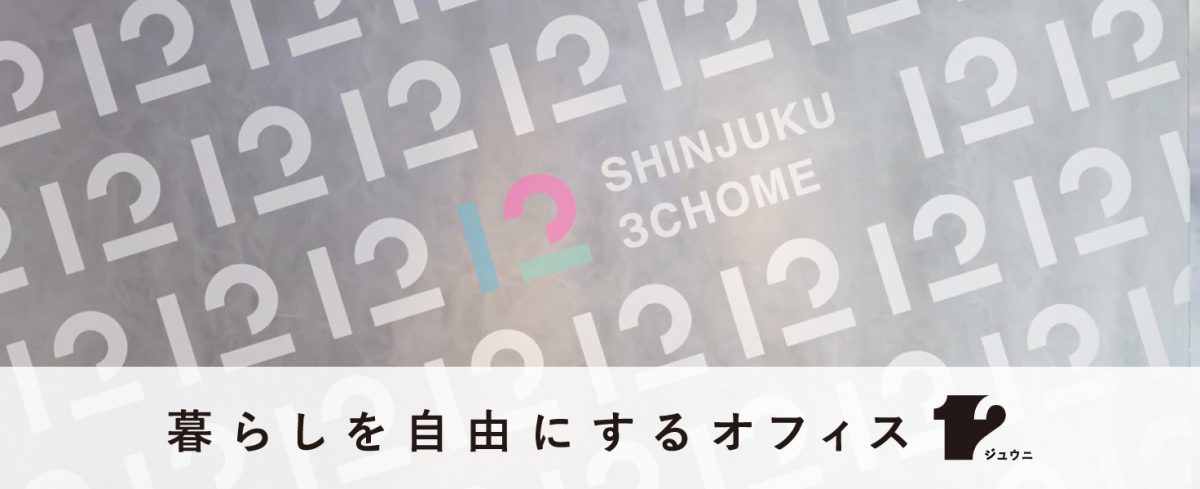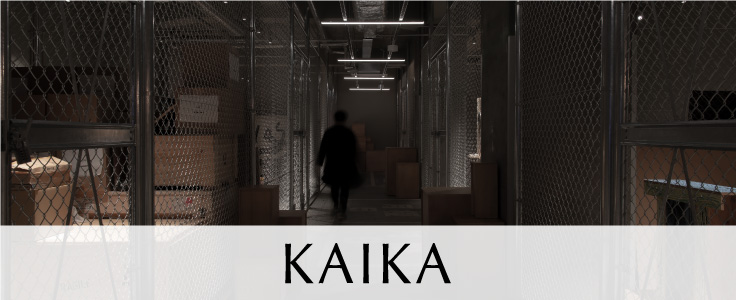世界のおやつを旅して
~ひとくちで感じる、暮らしのちがいと豊かさ~
立教大学卒業後、株式会社バーニーズジャパンに入社。アパレル業界を経てパティシエに転身。ザ・ペニンシュラホテルのフレンチレストランやパティスリーなどで修行を積んだ後、会員制レストランでシェフパティシエに就任。退職後は約1年にわたり世界各地でお菓子を作る旅へ。これまで50カ国以上を訪れ、500種類以上の世界のおやつを学んだ経験をもとに、お菓子ブランド「世界のおやつ」を主宰。企業や自治体、大使館などのプロモーション、レシピ開発、ワークショップ講師、お菓子ケータリングなどを通して、旅とお菓子のストーリーを届けている。
「SEKAI NO OYATSU」は、「おやつの旅」を通して、日々のくらしを少し丁寧に、少し豊かにすることを目指すプロジェクトです。世界の台所で教えられたのは、派手さではなく「暮らしに根ざす小さな習慣」でした。朝の1杯に添える素朴な焼き菓子、作り手が代々守ってきた配合、家族が気軽に分け合う時間──そんな断片が集まると、食卓の風景はじわりと変わります。 今回は、これまで50カ国以上を訪れ、500種類以上のおやつを学んだ鈴木文さんに、幼い日の台所から修行時代、旅先での出会いを通して見えてきた「暮らしの視点」について伺いました。
「日常」に世界を差し込むように — 子どもの頃の記憶と最初の一歩
ー幼いころからお菓子が好きだったのでしょうか。心に残る最初の “おやつ” の記憶は何ですか?
実は子どものころから「お菓子大好き!」というタイプではありませんでした。母の購読していた雑誌の巻末に、ちょこっと載っているお菓子のレシピを、切り抜いてたまに作っていた程度。それでも生地が膨らむ瞬間や焼き色がつく様子を見るとワクワクして、私にとってお菓子づくりはちいさな実験のような感覚だったんです。高校や大学では趣味でチーズケーキを焼いて友人に配り、「どうやったらもっとおいしくなるか」を試していました。社会人になってからも続けているうちに「これって人にお金を払って買ってもらえるのかな」と思う瞬間が来て。思い切って近所のカフェに飛び込みで持ち込んでみたんです。ほとんど断られましたが、2軒だけ置かせてもらえるようになり、朝に届けて出社し、帰ってから作るという生活が続きました。ある日そのうちの1軒から「ロシアの民話に出てきそうなお菓子を作って」と頼まれ、文献を参考に水玉模様のキャンディロールを提案したら、それがたまたまテレビで取り上げられたんです。その瞬間、お菓子には味だけでなく物語が必要だと強く感じ、もっと学びたいという気持ちが抑えきれなくなりました。
当時まだ25歳で、専門学校に通う選択も考えましたが遠回りに思え、まずは現場で学ぼうとフランス菓子店に履歴書を送りました。運よく採用されましたが、そこからはまさに修行の日々。朝5時出勤、帰宅は夜22時。体力も精神もギリギリの状態で、日曜の夜にシェフと電話を繋げて練習するのが唯一の復習時間でした。最初は技術や手順を覚えることに必死でしたが、だんだん自主練も減ってきて、空き時間に勉強の一環でフレンチレストランにデザートを食べにいくようになったんです。
そこでレストランデザートの世界に魅了されました。それまでは、小さな世界観の中で作り上げる世界だったのが、もう少しパフォーマンスの範囲が広くなって、直径20cm以上の皿の上で組み合わされるお菓子の世界へ。こうして、次はホテルの中のレストランに片っ端から履歴書を送ります。
そこでたどり着いたのがザ・ペニンシュラ東京のフレンチレストランで、あの現場の阿吽の呼吸や仕上げの緊張感は今でも忘れられません。みんなのリズムが合ったときに生まれる1皿の気持ちよさが、自分にとっての大きな学びになりました。
その後、ゼロから自分のデザートを考案したいという想いが高まり、オリエンタルランド内の会員制レストラン「club33」のシェフパティシエへ。そこでの開発経験や、お客様の時間に寄り添うものづくりが、のちに〈SEKAI NO OYATSU〉という形で世に出ていく下地になっていきます。振り返ると、台所の片隅で母の作る姿を眺めていたあの時間が、いつのまにか自分の仕事の根っこになっていたのだなあと、しみじみ思いますね。

おやつが教えてくれた、くらしの多様性
ー 「SEKAI NO OYATSU」が生まれるきっかけはどこにあったのでしょうか。旅に出ようと思った理由を教えてください。
club33でデザート開発をしていたとき、マカロンはフランス発祥だと思っていたのに、調べてみると起源はイタリアに近い話があり、自分が表面しか見ていなかったことに恥ずかしくなりました。それを機に、流行や見せ方だけを追いかけるのではなく、作り手の暮らしや歴史を知ることが本質だと思い、現地に行って直接学ぶ決意をしました。
当時はSNSも発達していなくて、情報は限られていたから、地図を片手に人に聞き回るしかありません。いわゆる「当たって砕けろ」精神で、飛び込みで現地の人に話しかけ、台所に入れてもらったり、家庭やお店を覗かせてもらったりしました。そうして1年ほどで55カ国を回り、500種類以上のおやつと出会う旅になったのですが、国ごとにおやつの役割や作り方、食べられる場面がまるで違うことを実感したんです。
ー旅先で印象に残ったエピソードはありますか?
南米での経験は特に衝撃的でした。私の中のラテンのイメージは「明るくてウェルカム」というものだったのですが、実際に現地で作り手に話を聞こうとすると案外警戒されてしまうことが多くて、声をかけてもすぐに心を開いてもらえるわけではありませんでした。10回声をかけて、ようやく1回ちゃんと話してくれるかどうか、という感覚で。約束をすっぽかされることも日常茶飯事で、信頼を得るには時間が必要だと知りました。
現地で教わるレシピは、とにかく大ざっぱなんです。「芋を3つ、砂糖はこれくらい」とか「火にかけて感覚で見て」といった口伝えが中心で、計量や時間の数値がない。それでもあの場で食べるとすごく腑に落ちる味になるのは、気候や素材、調理の手際といった背景が影響しているからだと気づきました。帰国して同じことをやってみると、甘すぎたり水分が多すぎたりして違和感が出てしまう。試行錯誤を繰り返して、日本の食材や気候に合わせて調整する方法を見つけていきました。
結果的に、そうした「現場での学び」はレシピだけでなく、その土地の暮らし方をどう伝えるかという考え方にもつながりました。おやつは単なる嗜好品ではなく、家族や地域の時間を結ぶ道具でもある。いちパティシエとしてプロが作るお菓子ブランドを立ち上げると同時に、日本の食卓にも、もう少しラフで日常的なおやつの場面をつくりたいと思うようにもなりました。
現地の味を日本の台所で
ー 現地のレシピを日本の台所で試したとき、味や食感、工程のどんなところに違いが出ましたか?
帰国して最初にぶつかったのは、同じ材料でもまったく違う結果になるという現実。だから私がやったのは「そのまま再現する」ことではなく、現地で感じた味わいや食感の要素を日本の材料と調理環境に落とし込む作業でした。湿度や水分量、焼き時間を微調整したり、塩や発酵調味料を少し加えて味に深みを出したりと、何度も微調整を重ねました。そのプロセスを経て出来上がったのが、『世界のおやつ おうちで作れるレシピ100』(パイインターナショナル)です。レシピだけでなく、そこで出会った人の話や街の風景も一緒に届けたくて、背景のエピソードも大切にしています。

ー 特に思い入れのあるお菓子は何ですか?その理由も教えてください。

南米の「アルファフォーレス」は、私にとって特別な存在です。サブレのようなクッキーにコンデンスミルクを煮詰めたキャラメルクリームをはさんだもので、街中のキオスクから家庭まで本当にどこにでもあります。でも「ありふれている」からこそ、家庭ごとに守られている味がある。パラグアイで泊まった小さなホテルで、日本人移住者のお母さんと一緒に作ったとき、約50年前に日本からパラグアイに入植され、パラグアイの歴史とともに生き抜いてきたお話や、家族のアルバムを見せてもらいながらつくったことが、私にとって、ただのおやつ以上の味わいへと変わりました。
「日本人移住者として、日本とパラグアイをつなぐ架け橋になれれば…そんな想いを持ってパラグアイの文化を伝える手段の1つとしてはじめた」と、そのお母さんから聞いたとき、アルバムを見ながら胸がきゅっとなりました。そんなこともあってアルファフォーレスには思い入れが深く、帰国して真っ先に試作したお菓子のひとつです。作るたびにあの夜の台所の空気や、お母さんの話がふっとよみがえり、味とともに「誰かの人生」や「遠くの家族への想い」まで運んでくるように感じます。だから私は、レシピを書くときに分量だけでなく、そのお菓子が食べられる場面や作り手の物語をできるだけ添えるようにしているんです。
日常に取り入れるコツ — 肩肘張らないおやつの楽しみ方
ーお菓子作りって難しそう…と感じる方も多いと思います。無理なく楽しむコツってありますか?
敷居を下げることから始めるのが一番です。完璧な道具や材料がなくてもおいしく作れることを知ると、台所に立つハードルがぐっと下がります。私が現地で見た家庭の台所には特別な器具なんてほとんどなくて、あるもので工夫して作る姿が当たり前でした。
普段は買って食べているおやつを、月に1回くらいは自分たちで作ってみませんか? 正式な製菓道具がなくても、肩肘張らずに台所にあるもので上手く代用してみると割り切るだけで、そのハードルがぐっと下がると思います。完璧なスタンバイや完成より、誰かと一緒に作るという、その過程を楽しむことがもっと暮らしを豊かにしてくれるはず。

「暮らしを想像する力」を育むために
ー おやつって、子どもたちにとっても特別な存在ですよね。どんなふうに届けたいと考えていますか?
我が家の子どもは今4歳と7歳で、市販のお菓子も普通に食べますし「これは絶対にダメ」というルールは作っていません。けれど、一緒に作る時間は大事にしています。見た目がきれいでなくても、手がベタベタになっても構わない。豆腐を混ぜて白玉をふんわりさせる、みたいな小さな工夫を一緒にするだけで、子どもは「自分が手伝った」という満足感を持ちますし、味わい方も変わります。
海外で見たのは、台所が世代をつなぐ場所になっている光景でした。混ぜる音や香りで子どもが寄ってきて、「今なに作ってるの?」と自然に会話が始まる。そういう流れのなかで、材料や気候、誰が食べるかによっておやつの意味が変わることを伝えたい。レシピをただなぞるのではなく、「どうしてこの国では朝にこれを食べるんだろう?」とか「この材料はどこで手に入るのかな?」と想像する習慣を育ててあげたいんです。
「SEKAI NO OYATSU」のこれから
ー 今後はどんなことに取り組んでいきたいと考えていますか?
世界一周のときはインプットを100%にして、その後7年かけて日本でアウトプットを続けてきました。これからはインプットとアウトプットのリズムをもう少し滑らかに、行ったり来たりできるようにしたいと思っています。旅の熱が高いうちに出かけて、感じたものをすぐに日本で形にする。そうすることで記憶の温度を保ちながら、暮らしに還元していけるのではないかと。
また、子育てとの両立を考えた旅の仕方にも変化が出てきました。長期間1人で滞在するのではなく、家族で短期滞在して子どもにもその場の空気を感じさせる「学びの旅」を増やしたい。台所に立つ時間を共有することで、旅が日常の一部になる――そんな風景を自分の子どもにも見せていきたいですね。
私が表現したいのは、正解ではなく「想像する余地」です。おやつひとつにも、その土地の気候や歴史、誰かの記憶が詰まっていると気づくと、味わい方が変わります。まずは気軽に一口、自分の台所で試してみてください。そこから小さな会話が生まれ、隣の人の顔が少し違って見えるようになるかもしれません。
おやつは、遠い国の暮らしも、身近な日本の暮らしも、そっと自分の食卓に差し込むことのできる小さな入口です。気負わずに始めてみてください。どこかで出会った味や話が、暮らしを少しだけ豊かにしてくれるはずです。